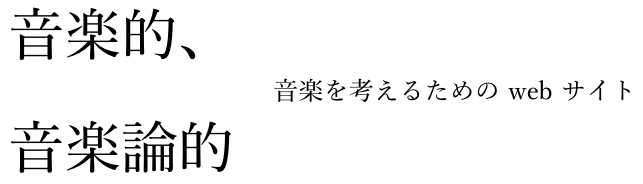音楽は哲学的にどう議論されているのか、あるいは議論されてきたのか。その大枠を捉えるために最も有効な手段のうちの1つが、「事典を調べる」でしょう。ということで、様々な哲学・思想系の事典で音楽に関する項目をノートをつくってみることにしました。調べてみるとけっこうでてくるものですね。
第1回は、発売以来、哲学・思想系の事典のスタンダードとして君臨しつづけているとわたしが勝手に思っている、『岩波 哲学・思想事典』(岩波書店)です。 と、言いたいところですが、ちょっとあんまり面白いのが載ってなかったので、『岩波 哲学・思想事典』が出る以前に長く哲学・思想系の事典の王者に君臨していた(と、これも勝手にわたしが思っている)平凡社の『哲学事典』。
これからみていくことにしましょう。もちろん、複数項目ありますので、何回かに分けます。今回は、そのまま、ずばり、「音楽」の項目です。
- 参考事典・ページ: 『哲学事典』(平凡社、1971)p. 199 – 200
- 項目名: 音楽
- 執筆者: 不明
- 参考文献: なし
※以下の「内容」中、段落ごとの表題、関連しそうなウェブサイトや文献へのリンクを勝手に挿入しています。
音楽の語源
- 音楽の語源は、ギリシア語のムシケ、つまりミューズの芸術 = 技術 である
- 音楽とは何か、音楽の本質とは何か、については、哲学史上長い議論の歴史がある。
※関連ページ: 古代ギリシア(1)「ムーシケー」について
古代ギリシア
- 音楽は原始時代、主に呪術的なものだった
- 古代ギリシアでも、やはりはじめは呪術的なものだったが、やがて学問の対象となった
古代ギリシアにおける音楽観 (1) ピュタゴラス
- 古代ギリシアにおける音楽観は, ピュタゴラスから始まった
- 数の神秘を説いたピュタゴラスは、認識論的・宇宙論的とも言える音楽論を展開した
- つまり音楽を、ひとつの宇宙の法則性の象徴、真理、学問として捉えた
※関連ページ: 古代ギリシア音楽(4)ギリシアの音楽理論家: ピュタゴラス
古代ギリシアにおける音楽観 (2) プラトン, アリストテレス
- ピュタゴラスに対してプラトンは、音楽を知的・道徳的教育としてとらえた(『国家』)
- またアリストテレスは、プラトンのように音楽における道徳的教育の有用性を認めていはいたが、他方で、人間の苦悩を癒し、また、美的快楽を生む有用性も認めた(『政治学』)
※関連ページ: 古代ギリシア音楽(6)ギリシアの音楽理論家: アリストテレス
古代ギリシアにおける音楽観 (3) アリスクセノス
- その後、アリストテレス派のアリストクセノスが、近代的な音楽観を萌芽がみられる古代ギリシアの音楽理論を集大成した(『ハルモニア原論』)
※関連ページ: 古代ギリシア(7)ギリシアの音楽理論家: アリストクセノス
中世
- 中世では、宗教的な戒律や予言、神の掲示への直観へとひとびとをみちびく「ことば」が音楽の支配原理となった
アウグスティヌス
- 中世に音楽について論じた代表的な哲学者はアウグスティヌス
- ただしアウグスティヌスの音楽観は、必ずしも「ことば」のない音楽 = 純音楽的なものを否定してはいない
- アウグスティヌスはピュタゴラス的な数論をうけつぎ、「音楽は、音のうごきをよく整える知識である」とした
※アウグスティヌスの音楽論は、著作集第3巻で読める
中世後期
- また、中世後期になると、実践的な音楽学がアルス・ムジカとして7つある自由学芸のうちの1つになり、修道院や大学の哲学部の教科の1つになった。
※関連ページ: 中世音楽(6)まとめ
ルネサンス
- ルネサンス以降、宮廷や貴族のサロンでマドリガーレが演奏され、オペラが発明された
- 市民の間にも楽器が日常的な備品として広がった。
- こうした動向にともなって、人文主義的な感情化された音楽観が広まった。
- 美学的研究や理論においては、中世的・スコラ的な合理主義が残っていた。
※関連ページ: ルネサンス音楽 まとめ
ライプニッツ
- ライプニッツは、「音楽は霊魂がみずから数えることのできない、隠された数学的実践である」という音楽観をもっていた
- つまりライプニッツにとって、美学的研究や理論における音楽は数学的な世界像であり、合理主義的探究だった
デカルト、メルセンス
- ライプニッツの一方、『音楽提要』を著したデカルトや、メルセンスは、和声によって音の「理性」を意識の内側から捉えようと試みるなど、二元論的な音楽論を展開した。
※参考サイト: Marin Mersenne
※参考論文: 石井 忠厚「デカルトの≪音楽提要≫」
バロック時代
- バロック時代の音楽は、デカルトやメルセンスの音楽論の実践といえる
- つまり力動的なリズムや情緒表現に理性的規制力をもとめた
- 18世紀には、科学がさらに発展するとともに、新しい民衆的・市民的力を基盤とした大交響曲や器楽曲が盛んになる
- また、啓蒙思想が旋律的の自然な表出性と器楽的な合理性を結びつけ、オペラ・コミーク(ルソー)やオペラ・ブッファをうんだ
※関連ページ: バロック音楽(2)オペラ , バロック音楽(16)まとめ
※参考サイト: ルソー音楽思想関係文献案内
ロマン主義
- 19世紀のロマン主義的な音楽観では、感情的・文学的把握が強調された
※関連ページ: ロマン主義の音楽(1)概要
ショーペンハウアー
- ショーペンハウアーはライプニッツの定義をもじり、「音楽は霊魂がみずから哲学することを知らない、かくれた形而上学的実践である」と述べた。
- ショーペンハウアーの音楽観は、ヴァーグナーやプフィッツナーをはじめとする作曲家に影響を与えた。
- ショーペンハウアーは芸術体験のうちに「意志と表象」とのあいだにある人間存在の目的を認め、音楽派世界そのものの究極の陰影であると考えた。
ニーチェ
- またニーチェはワーグナーの悲観的パトスを逃れようとして、未来的楽天主義によってデカダンスを超克しようとした。
音楽家たちによる議論
- ロマン主義においては、音楽家も優れた思想家だった。
- ホフマン、シューマン、ベルリオーズ、ワーグナー、ブゾーニらが活発に議論した。
※関連ページ: ロマン主義の音楽(7)シューマン, ロマン主義の音楽(10)ワーグナー
ハンスリック『音楽美論』
- ハンスリックは感情内容説に対立した立場から直感形式説の純粋主義を唱えた。
- しかしその後、実証科学の興隆期となり音楽美学も科学的動向の影響があらわれていった。
20世紀
- 20世紀に入ると、調性体型という古典音楽の秩序は崩壊をつづけた。
ドビュッシー
- 音楽は、音は旋律や主題から解体されて、ベルクソンのいう生の根源的源泉———つまり純粋持続の直観的な把握をその原理としだした。
- このような音楽の例として、ドビュッシーが挙げられる。
※関連ページ: ロマン主義の音楽(16)印象主義
シェーンベルク
- 音楽における音は旋律や主題から解体の例としては、印象主義の他、シェーンベルクが挙げられる
- シェーンベルクの表現主義は、第一次世界大戦前後の危機の時代の音楽を表現した
- シェーンベルクは表現主義以降、やがて新しい音響のリアリティーとして12音のセリーの技法を確立した。
関連ページ: 20世紀前半の音楽(2)新ウィーン楽派: 表現主義, 20世紀前半の音楽(9)新ウィーン楽派: 十二音技法
新古典主義、電子音楽
- 音の主知的な構成をこころみたストラヴィンスキーの新古典主義。
※関連ページ: 20世紀音楽(8)新古典主義
- あるいは未来派の詩人・作曲家のルッソロの騒音音楽をうけついだような第二次大戦前後のミュージックコンクレートや電子音楽。
※関連ページ: 20世紀前半(4)イタリア未来派, 20世紀後半(4)テープ音楽・コンピュータ音楽
- こうした 20 世紀の新しい音楽から聴きとることのできるのは音楽を「音」に解体したところから問い直そうとする姿勢で、
- 「音」をオブジェすなわち〈物体〉として認識する実在的な把握ともいえる。
アンセルメと現象学
- アンセルメはあくまでも古典的な調性の体系こそに音楽の本質があるとして、現代音楽を批判した。
- しかし、そこにさえフッサールとサルトルの現象学的存在論を拠り所にしながら音楽の本質に迫ろうとしていた。
※参考サイト: Ernest Ansermet – AllMusic, Ernest Ansermet (Conductor) – Short Biography
クセナキス
- このような状況を音楽の1つの終末とは考えずに、新しい転換の時代として受けとめている作曲家たちは、時代の提供するさまざまなメディアや素材と切り結んであたらしい可能性を試みた。
- クセナキスは、数学の集合論やコンピューターによって作曲する統計学的音楽や記号論音楽を試みた。
- また、数学(論理)を作曲法の根底におさえながら、音楽と哲学とのあたらしい融合を試みた。
1971年初版なので、項目の最後がクセナキスで終わっているあたり、ちょっと古さを感じざるをえません。が、古代ギリシアから現代に至るまでの、音楽史およびそれに影響を与えた哲学・思想を紹介するという、かなり丁寧な内容になっています。執筆者が分からないのと、参考文献がないのが残念ですね(この事典はほとんどの項目そうなんですが…)。
次回は「音楽学」です。