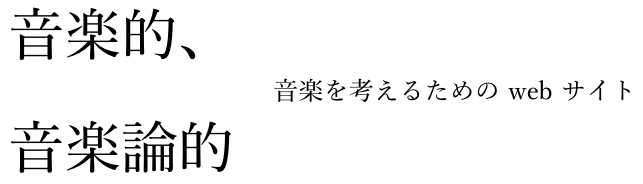仕事や勉強をしているときに音楽を流すことがあるでしょうか? その音楽があなたのパフォーマンスにどのような影響を与えているのか、気になったことはありませんか? 音楽が認知タスクのパフォーマンスにどのような影響を与えるかについては、これまで多くの研究が行われてきましたが、その結果は一様ではありません。今回は、Lena Maria Hofbauer らによる「Background music varying in tempo and emotional valence differentially affects cognitive task performance: experimental within-participant comparison」(日本語タイトル: 「背景音楽のテンポと感情価が認知タスクのパフォーマンスに与える影響」)という論文に基づき、このテーマについて詳しく解説していきます。
続きを読む