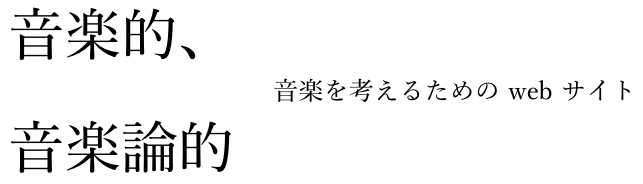さて、今回は楽譜の必要性(厳密に言うなら、「記譜」の必要性)について興味深い記述を紹介します。バッハ以後の音楽が、バッハ以前の音楽といかに新しいかを述べることで、バッハ以前は古い音楽 = 古楽だった、という説明のなかの部分です。
「一四世紀を代表する名オルガニスト、フランチェスコ・ランディーニは、「オルガン作品はただの1曲として残っていない」「自分のために楽譜を記す必要性を感じなかったわけである」(金沢正剛(2010)『新版 古楽のすすめ』音楽之友社 p. 33)
ちょっと引用の仕方がクソなのでまとめると、一四世紀(バッハ以前)にフランチェスコ・ランディーニというオルガン演奏家がいた。
しかしランディーニの作品は、声楽曲しか残っておらず、得意としていたオルガン作品が全く残っていない。なぜなら、自分が演奏するために作曲したのだから、楽譜を書く必要がなかったため、ということです(ちなみに声楽が残っている理由は、「他人に歌ってもらわなくてはならないから」(同書 同ページ))。
楽 譜 通 り に 弾 く あるいは 作 品 と は 楽 譜 で あ る などという、楽譜が重要視される傾向のある現代に比べると、この状況はかなり興味深いです。
もちろん、楽譜が重要視されるというのは、一部の(しかし主流である)ポピュラー音楽及び、いわゆるクラシック音楽に限定されるます。音楽には、現代であっても、楽譜が重要視されない音楽というのは、無数に存在します。しかし、例えば中高生がロックバンド活動をするにあたって、楽譜を読める = 音楽能力が優位 という考え方が蔓延っているのは事実でしょう。
しかし、『新版 古楽のすすめ』で紹介されているフランチェスコ・ランディーニの例からは、楽譜を読める = 音楽能力が優位とは限らない、というメッセージ(笑)が読み取れます。もちろん私が勝手に読み取っているだけです(笑)。
なお、先に言い訳しておきますが、別に 楽 譜 が 読 め な く て も 良 い とか、 楽 譜 は 必 要 な い とか、そういうことをメッセージとして受け取りたいわけではありません。単に、 楽 譜 が 絶 対 で は な い という考え方があるんだ、ということです。それに、先に引用した部分は、「記譜」の「必要性」がうんぬんであって、楽譜を読めるかどうかは話題になっていません(だから私の読みは曲解なのです(笑))。
『新版 古楽のすすめ』に戻ります。「楽譜の必要性」の例ですが、フランチェスコ・ランディーニだけではなく、あのバッハも挙げられています。
「《ブランデンブルク協奏曲》第三番ト長調第二楽章は、二つの和音が記されているにすぎない。」
「《ブランデンブルク協奏曲》第三番ト長調第二楽章」「バッハにしてみれば、音楽そのものは自分の頭の中にあり、それを自分で弾くことになっているわけであるから、わざわざ記譜するなどという面倒なことをする必要がなかったのである」
「もし二回目の演奏で、自分に不満足なところがあれば、二回目の演奏で別のやり方を試みればよいわけである。あるいは前回あのようにやってみたから、今回はこのようにやってみようか、などという自由もある。それが即興演奏の面白さである」
いやー、またも衝撃(笑)。「モテトゥス」の次くらいに衝撃。『〜 古楽のすすめ』を読む以前は、バッハの音楽というのは楽譜がキッチリしていて、カッチカチの音楽だという先入観がありました。しかしここの部分を読んで以来、そのイメージがかわりました。
私は《ブランデンブルク協奏曲》第三番の CD を2つ持っているのですが、聴き直すと全然違いました。すみません、それまで全然ちゃんと聴いてなかったです(笑)。
とにかく、楽譜に関する考え方、つまり「記す」「読む」「その通りに演奏する」というのは、音楽活動の一面でしかなく、これを絶対視する必要はない、ということでしょう。
しかし、一部の(主流の?)音楽においては、楽譜に関する能力が必要不可欠で、楽譜に関する能力を(そんなことする人なんていないと思いますが)無批判に否定してはならない、ということも注意しておかなければなりません。
もっと言えば、楽譜通りに演奏した上で、楽譜通り以上の豊かな音楽を表現しなければならない。ということでしょう。ということは、あれ? 楽譜を「記す」「読む」「その通りに演奏する」というのは超・基本で(笑)、「それ以上の豊かな音楽を表現する」ためには楽譜に関する能力を習得するよりも遥かに音楽能力が必要だと、そういうことになります。