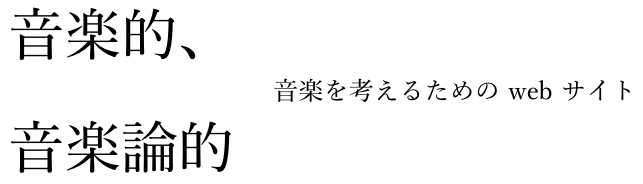音楽は哲学的にどう議論されているのか、あるいは議論されてきたのか。その大枠を捉えるために最も有効な手段のうちの1つが、「事典を調べる」でしょう。ということで、様々な哲学・思想系の事典で音楽に関する項目をノートをつくってみることにしました。調べてみるとけっこうでてくるものですね。事典ということで、1つ1つの項目のボリュームが大きいので、内容をかいつまんでの紹介になります。
前回まではコチラ。
- 哲学系の事典で「音楽」はどう論じられているのか?: 『哲学事典』(平凡社)「音楽」のノート
- 哲学系の事典で「音楽」はどう論じられているのか?: 『哲学事典』(平凡社)「音楽学」のノート
- 哲学系の事典で「音楽」はどう論じられているのか?: 『哲学事典』(平凡社)「音階」のノート
今回は、第1〜3回に引き続き平凡社の『哲学事典』から「音楽芸術論」です。
前回、前々回に比べるとちょっと哲学・思想っぽい項目です。みていきましょう。
- 参考事典・ページ: 『哲学事典』(平凡社、1971)p. 201
- 項目名: 音楽芸術論
- 執筆者: 不明
- 文献案内: なし
以下の「内容」中、関連しそうなウェブサイトや文献へのリンクを勝手に挿入しています。
音芸術としての音楽
- 「音芸術」というもとの意味では、音楽は組織だてられた音の領域内にふくまれる一定の音をなんらかの法則にしたがってかたちづくる芸術である
- 楽譜の発達にともなって、作品の創造者とは別に、鑑賞に対して註解をする演奏家をもつことになったのは、音楽の一特性である
- 舞踊や文芸とともに時間芸術のうちに数えられ、彫刻や絵画とともに空間芸術のうちに数えられる建築と対比させられる
音楽と芸術の対比
- たとえば建築は凍れる音楽である、といわれている
- しかし音楽の天才にみられるような早期の完成された創作ないし演奏活動のようなものは建築家にはみられない (建築学の知識なしにはりっぱな建築芸術は成り立ちえない)
- しかしモーツァルトやメンデルスゾーンの初期の作品は、必ずしも厳密な意味での音楽学を前提とはしていない
- しかし、そのことは音芸術にとって音楽学があまり必要とされないといことを意味しない
※関連ページ: 古典派(5)モーツァルト: 生涯, 古典派(6)モーツァルト: 声楽曲, 古典派(7)モーツァルト: 器楽曲, ロマン主義(6)メンデルスゾーン
ヨーロッパの伝統における音楽
- ヨーロッパの伝統では、音楽は実際の芸術であるよりも音楽学である場合が多かった
- 近代においても現代においても、広義の音楽学は音芸術と不可避の関係にある
- たとえばメシアンにおける旋律・リズム・和声の新しさは、古代や中世の音楽史的知識だけでなく、東洋音楽についての比較音楽学的認識、音律論や広義の音響学的探究を前提としている
- オンド・マルトノのような新電気楽器の使用も、こういった音楽学的探究に基づく
- シェーンヴェルク、ワーグナー、大バッハへとさかのぼっても、同じことがいえる
※関連ページ: 20世紀後半(3)ダルムシュタット国際現代音楽夏期講習会, 20世紀前半(2)新ウィーン学派: 表現主義, ロマン主義(10)ワーグナー, バロック(14)バッハ
※関連サイト: The ‘Ondes-Martenot’ Maurice Martenot, France, 1928
芸術としての音楽の根本的な特色
- 要するに音芸術は単に娯楽でも代用哲学(アリストテレス)でも代用道徳でもなく、もっとも純粋に時間と関係する高度に冷静的な芸術である点に根本的な特色がある
- ジセル・ブルレによって基礎付けられたような音楽の新しい時間論的探究の発展が期待されている
前回、前々回の「音楽」「音階」の項目に比べるとずいぶん短いですが、音楽「芸術」といった場合、その音楽は学的な対象である、という執筆者の意見がみてとれます。これは逆に言えば、芸術としてではない音楽をみとめているということにもなりそうですね。
次回は「音楽美学」を予定しています。