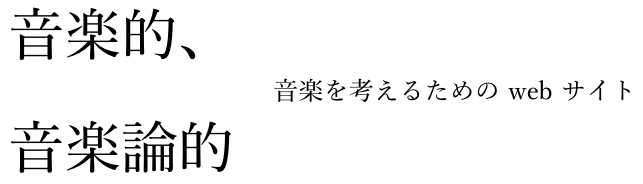本書は、1998年のスモールの著作の邦訳である。
1.動機
本書は以前から気になってはいて積読状態だったのだが、キェルケゴール『キリスト教の修練』における芸術非難を受けて、この非難から芸術を(おおげさでおこがましいが)〈救う〉考え方はないか、と読み始めたのが本書である。
キェルケゴールは『キリスト教の修練』において、芸術が「讃美」であるかぎり、宗教にとって必要ではないと主張する。では、讃美ではない芸術は可能なのだろうか。キェルケゴールが、芸術とは讃美である、と主張したのは、芸術は作品であると誤解したからではないだろうか。本書のように、芸術を〈行為〉として捉えることができれば、讃美ではない芸術への可能性が開けるのではないだろうか。
これに対する結論としては、(「宗教」や「讃美」が主題で扱われているわけではないが、内容から凡そ推測すると、)本書で述べられている〈行為〉は、〈讃美に回収されるであろう行為〉である。したがって、『キリスト教の修練』においてキェルケゴールが非難した芸術を〈救う〉ことは本書の理論においては不可能であろう。
以上のように、キェルケゴールにによる芸術小論のようなものに触発されて読始し、それに対する結論としては、けっきょく解決されはしなかった。しかし本書を通じて、私の中での長年の問いである〈音楽とは何か〉への回答として何となく〈これではないか〉と〈ぼんやり思い浮かべていた或る考え〉が、少し確信へと近づいた。以下ではこれについて手短かに述べたい。
2.ミュージッキングとは、その脆弱性
スモールによると、音楽それ自体は存在せず、存在(ここで「存在」という単語を使用して良いのかどうかはわからないが)するのは「ミュージッキング」=「音楽する」である。これにより、或る音楽作品は優れており、他の音楽作品は劣っているなどという考え方は相対化される。
しかし、ミュージッキングという理論を導入したところで、次の問いは残されたままではないか。すなわち、「音楽する」と「する」の区別は何か。換言すれば、〈音楽行為〉と〈その他の行為〉の差は何なのか、という問いである。
この問いを立てることで、(そもそも「何か」という問いの形式に音楽それ自体という先入観が蔓延っている可能性は否めないにしろ)〈音楽とは何か〉あるいは〈ミュージッキングとは何か〉という問いは循環に陥るかのように見える。すなわち、〈音楽それ自体〉は存在しないが〈音楽する〉は存在するのであれば、〈する〉を〈音楽する〉たらしめるそれとは何か、を問わねばなるまい。しかるに、〈する〉を〈音楽する〉たらしめるそれとは、〈音楽それ自体〉ではないのだろうか。しかし、〈音楽それ自体〉は存在しない。
もちろんこのような循環のないよう、スモールは、人類学者ベイトソンの理論に依拠しながら、また、「儀礼」「神話」「隠喩」という語句を中心的に使用しながら、ミュージッキングをその他の行為と区別できるよう特徴付けている。しかしこの特徴付けには脆弱性が認められ、したがって次のような2つの疑問が残る。
1つ目に、スモールはミュージッキングの理論的基盤としているといっていいほどベイトソンの考え方に依拠しているが、その依拠の仕方があまりにも無批判に過ぎるのではないか。特に、〈心〉や〈関係〉といった語句を、スモールはどのように理解しているのか(この疑問に派生して、ベイトソンの考え方が(すなわち、ミュージッキングの理論的基盤の基盤が)自然科学に依拠しているが、この自然科学の正当性はどのようにして保証されるのか)。なお、この点に本書に対する最大の違和感があるのだが、この違和感を検証するためには、スモールの挙げている音楽以外の参考文献を逐一批判しなければなるまい。
また2つ目に、これが最大の脆さであろうが、「儀礼」「神話」「隠喩」という語句を中心的に使用することでスモールはあらゆる芸術を行為から捉え直そうとするが、そうであるならミュージッキングに限定する必要はないのではないか。なぜことさら〈音楽する〉にこだわるのか。〈芸術する(アーティング?)〉という理論に拡充するべきではないか。
3.音楽とは何かへの試論
本書からは、以上のような〈ミュージッキングの特徴付け〉に対する2つの疑問への回答は得られまい(もちろん、反論はいくらでもできようが、割愛する。なお、2つ目の問いについて簡単に言えば、音楽それ自体を想定してしまう先入観が原因であると反論できよう)。そうだからと言って、ミュージッキング理論が全く無効だというわけではない。というのも前述の通り、本書を通じて私の中でぼんやりと考えていた〈音楽とは何か〉への回答が、確信へと近づいたのだが、その回答は次の通りである。
「音楽とは、音に対する人間の精神の働き」である。
何とありふれた、何と至極当然の回答であろうか。こんなことはうすうす気付いていた。この気付きが、本書によってほとんど盲(妄)信ともいえる確信へと達したのだ。
もちろん、この回答に対する反論も想定できる。すなわち、人間が或る音を音楽と認識する際の精神の働きと、音楽と認識しない際の精神の働きの差は何か(また、次のような問いが当然残る。すなわち、〈働きとは具体的に何を指すのか〉。さらには、音楽以外の問いであるが、〈精神とは何か〉。これに関する考察は、別途機会を設けたい)。この反論については、次のように回答できよう。すなわち、この反論は、〈人間の精神を働かせた音はすべて音楽なのか〉と換言できるであろうが、それは(例えば、あらゆる森羅万象の根拠を〈神〉と呼んでいいかどうかといったような)〈呼び方〉の問題であり、(かなり文法的に奇妙な記述だが)すべての音は音〈で〉ある限り音楽〈で〉ある可能性〈で〉ある、と(このように回答したところで、未だ様々な反論が想定できようが、反論の反論はこの文章の目的ではない)。
———、長年問い続けた末にこんな当然の確信しか得られなかった瞬間、気持ち悪くなった。というのも、(思い上がりも甚だしいが、)音楽にかけられた魔法が解けたような気分だったからだ。
しかし、ここから始めなければなるまい。「音楽とは何か」への思い巡らしは新たな出発点に立ったのである。というのも、この回答の有効性を確かめなければならない。また、確かめたことを文章化しなければならない(そうしないことには、音楽に対する憧れが、これから生まれた意志が、弱まりそうなのだ。いや、もう既に弱まりつつある)。換言すれば、導出された確信を応用するという、言わば終わりの始まりである。そのために、もう少し音楽活動 = ミュージッキングを続けることにしよう。
すべてを正当化しよう。否、すべてが事実だと、そして、事実ではないと、〈認めよう〉。
4.結語、追記
以上、ミュージッキング理論とこれに触発されて確信した私の音楽への見解を〈手短か〉に述べてきた。前述の通り、本書の理論的基盤には脆弱性が認められるので、内容に全面的に同意することは難しい。ただ、繰り返すが、本書によって私は、音楽に対する確信を手に入れることができた。この意味で、本書は私にとって〈正しい〉。
また、〈音楽とは何か〉という問いが、倫理に関わるのではないか、私にとっては新しい視座が与えられた。この点についてもいずれ、思い巡らしてみたい。