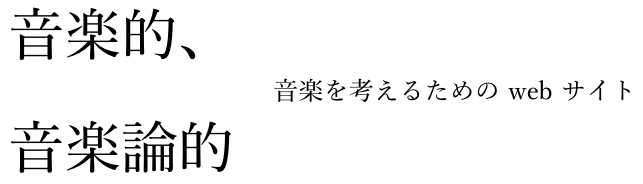「聴き方」というタイトルだけど、
実際には「音楽を語る」ことが議論の中心の本。
音楽を「語る」という行為は、最終的に不毛だと思う。
これは著者も言っているし、俺個人としてもそう思う。
でもそれは聴き手にとってのみで、あらゆるレベルでの作り手にとっては、
語ること、言葉にすることは、音楽にとっては不可欠になる。
それに、音楽を「語る」という行為が不毛であることは、
19世紀の西洋音楽社会に一般化した、
音楽「公演」と、「批評」と原因がある(らしい)。
ということを行ったり来たりしながら、
ちょいちょい歴史的なエピソードも入れながら、
結局何が言いたいのか知らん、と思った。
けっきょく音楽を語るという行為が、
少なくとも筆者にとっては良いのか悪いのか、
そこら辺が釈然としないと言うか。
面白いのは過去の偉人の著作からの音楽に対する言及の引用。
で、三島由紀夫とカントが芸術としての音楽に対してそこまで積極的な評価を下していなかったらしい。
三島の場合は、
音楽に対する得体の知れなさを感じていて「手に負えない」的な嫌悪感。
だからまったくつまらないものとして、
バッサリ切っていたというわけではない。
カントはバッサリだったらしいけど。
音楽に対して語る哲学者は結構多くて、
そのどれもが音楽を積極的に視ているので、
カントが音楽に対して消極的だったのは、以外と言うか、
まぁ、自分が無知だったと言うか。