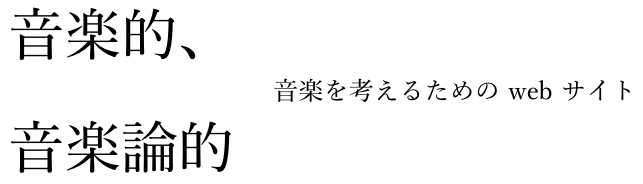田村和紀夫『音楽とは何か ミューズの扉を開く七つの鍵』(2012年、講談社)「第4章 音楽はリズムである」のノートです。なお、当エントリー中の引用部分は、特に断りのない限り同書からになります。以下も参考にしてください。
さて、前回のエントリー「舞曲への接近 — 大衆化」では、田村和紀夫による、音楽において踊りの要素が増えることでこの「芸術性」が薄れ「大衆性」が濃くなる(p. 112 – 113)という意見に対し、ちょっと待てこのヤロー(つまり、「芸術性」ってそもそも何? というか「芸術性」という単語が無批判に価値の高いといったような意味で使われていないか?)とツッコミを入れてしまったのですが、今回もその延長です。話題はポップスになります。
ということで、ここからいわゆるクラシック音楽にとどまらず、ポピュラー音楽における踊りと芸術性・大衆性の関連について説明がされているのですが、だいたいまとめると以下の通りです。
ジャズ
- 踊る音楽: スィング・ジャズ(1930年代)
- 聴く音楽: モダン・ジャズ(1940年代から60年代)
⇒「踊る音楽」から「聴く音楽」への飛躍
ロック
- 踊る音楽: ロックンロール(1950年代)
- 聴く音楽: ロック(1960年代)
ダンスミュージック
- 1970年代以降、「単調なダンス・ビートが音楽シーンへと徐々に浸透」
- 田村和紀夫の意見: そう長くは続かないだろう
と、以上のようにポピュラー音楽史を非常に乱暴にですね(笑)、ざっくり概観されるのですが、つづいて次のように締めくくられます。
「基本になるのは、踊りへの接近は「大衆化」、離反は「芸術化」という傾向を示すことです。ポピュラー音楽であるだけに、その様相は激しく、また多彩です。」(p. 115)
うーん(笑)、ちょっとコメントに困りますよね・・・、もちろん、こういった20世紀以降のポピュラー音楽の歴史を記述する際に、あらゆる「例外」を取り込むと記述することのほとんど不可能なのは確かです。だから、ここで田村和紀夫が述べているのは、大まかな傾向としては歴史的事実、と言えるのではないでしょうか。
ただ、まー、何と言うかですね、田村さん、やはり「音楽 = 西洋音楽」という図式から脱しきれていないような印象があるんですよねえ・・・。もしそうだとすると、こういった「踊る音楽」、ひいては音楽全体に対する一面的な理解しかできていないような気がするんですけれども・・・。いくら「選書」だから「解り易く書く」というのが執筆姿勢でもですよ、ちょっと乱暴過ぎな気がしますけど・・・、PHP文庫とかにある「これ一冊で分かる」シリーズじゃないんですから(笑)
あー、あとですよ、「単調なダンス・ビート」というのも、ちょっと大きな誤解の生じる可能性があるといいますか、黎明期のダンスミュージックについては知りませんけれども、ハウスやテクノ、ヒップホップといったクラブミュージックになってくると、「単調」なようで実はけっこう微妙にズレを作ったりしていますので。仮に「わかりやすさ」が音楽の大衆化の特徴(p. 112)であれば、いや、ダンスミュージックほどわかりにくいものはないですよ。ダンスミュージックこそ芸術になってしまいます。何故かというと、一聴すると解り易いビートなんだけど実は採譜することを無意味化する程の微妙なズレをたくさん生んでいた! てなって、これ、捉えようによっては分かり難さの極致(笑) だと思うんですよね。
それで、そもそも、「基本になるのは、踊りへの接近は「大衆化」、離反は「芸術化」という傾向を示す」というのは、これは田村和紀夫の意見なのでしょうか、それとも音楽学の一般的な意見なのでしょうか。ちょっとこの辺も判然としません。
ただまあ、前回のエントリーと言っていることがカブりますが、「大衆化」や「芸術化」という単語は、これ自体に客観的な価値基準があるわけではない、ということは、ワタシの意見として強調しておきたいところです。
あ! ちょっと思い付いてしまったんですけど! 書きながら! 本書のこの部分(「踊りの音楽」における「大衆化」「芸術化」について)の違和感というのは、「大衆化」と「芸術化」をあたかも反意語のように使用していることに由来するのではないでしょうか!? いやー、だってさー、「芸術性」の反意語は「大衆性」ではないですよ。