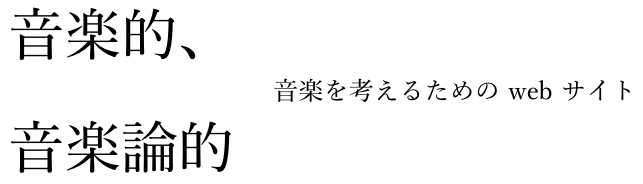2011年11月3日、国立新美術館にて『没後120年 ゴッホ展』を鑑賞した。当展覧会は「1.伝統」、「2.若き芸術家の誕生」、「3.色彩理論と人体の研究 – ニューネン」、「4.パリのモダニズム」「5.真のモダンアーティストの登場 – アルル」、「6.さらなる探求と様式の展開 – サン・レミとオーヴェール・シュル・オワーズ」の6部構成であり、画家ゴッホの芸術家としての成長の軌跡を辿る構成であった。あいにく、人出の多かったため、ゆっくり鑑賞というわけにはいかなかったが、以下に印象に残った作品についてのメモを記す。
展示番号78: フィンセント・ファン・ゴッホ『自画像』(1887)
まずこの絵画を観た。視線にのみ奥行きを感じる。それ以外は、彼の特徴的な、と言っても俺の印象でしかないが、画法は認められない。
展示番号1: フィンセント・ファン・ゴッホ『秋のポプラ並木』(1884)、 展示番号2: フィンセント・ファン・ゴッホ『曇り空の下の積み藁』(1890)
この2つを見比べることで、わずか6年に間に画家がどれほど技術的確立を成し遂げたのかが、特に1890年の絵画(展示番号2)の強烈な色彩(山吹-青)によって迫ってくるのが分かる
彼が、いかに異端だったか、当時において唯一無二だったか。
展示番号3 – 6: テオドール・ルソー『ジュラ山脈高地を下る牛』、ジャン・フランソワ・ミレー『漁師の妻』、ギュスターヴ・クールベ『マグロンヌの地中海風景』、シャルル・ドービニー『四月の月(赤い月)』
1886年 – 1890年のゴッホ以外の画家の作品は、いかに1886年のゴッホの絵画と似ていることか。それほど1890年において彼(=ゴッホ)が異端だったのか。
展示番号7 – 9(ウィレム・ルーロフス『コルテンホーフ近くの湖』、ヨゼフ・イズラエルス『夕暮れ』、テオフィール・デ・ボック『河の景観』)も3・4・5・6と同じにすぎない。相互的影響。
展示番号10、11: フィンセント・ファン・ゴッホ『ヤーコブ・マイヤーの娘(バルグの教則本のホルバインの素描による)、『ヤーコブ・マイヤーの娘(ホルバインによる)』
この2作品を見比べると、展示番号10において、ゴッホがいまだ発展途上だったことが分かる。天才は最初から天才(=完成)ではないのだ。
展示番号19: フィンセント・ファン・ゴッホ『炉端の少女』
しかし・・・、この得も言えぬ喪失感―――、このまったく模倣できていない素描は、わざと(=意図的)なのか。
展示番号20: フィンセント・ファン・ゴッホ『麦藁帽子のある静物』
静物に対しては、1881年の時点である程度完成(※)している。しかしこれは未だに我々の知っているゴッホではない (※師の下で描いたとのこと)
展示番号21: アントン・モーヴ『オランダ風納屋と差し掛け小屋』
画家たちはすでに、外(=屋外)へ出ている。
印象派との関連は?
展示番号35: ウジェーヌ・フロマン(アルフレッド・エドワード・イームズリーの原画による)『羊毛工場での労働』
「スピード」が(も)重要なのだ!
展示番号12、13: フィンセント・ファン・ゴッホ『掘る人(ミレーによる)』、ジャン・フランソワ・ミレー『掘る人』
ゴッホの作品(12)の方が、幾分〈ぼやけ〉ている(=細部が省略されている)。ただ、ここには思想(=プロレタリア)がある。
展示番号14: フィンセント・ファン・ゴッホ『掘る人』1881
画家であれば誰しもがそうであるように、ゴッホも真実を描こうとしたのだ。足元、靴をまたぐ1本の葦がその証拠である。
展示番号15: フィンセント・ファン・ゴッホ『掘る人』1881
この作品は展示番号14の下描きか? わからない。
(展示番号14・15について)ゴッホの描く人物はデフォルメされている。どのように? 輪郭が特徴なのか? こわばっている。角ばっている。
展示番号16: フィンセント・ファン・ゴッホ『掘る人』
展示番号14・15とは大きく構図が変えられる。人物左、スコップの表を向けることで、いくぶんか静止の中の躍動を感じる。
展示番号17: フィンセント・ファン・ゴッホ『籠を持つ種まく人』
これは意図的なのか、それとも未熟なのか、胴体と首のバランスがおかしい。
展示番号18: フィンセント・ファン・ゴッホ『種まく人』
展示番号17と同様。腕の遠近法も確立されていない。
展示番号23・24: フィンセント・ファン・ゴッホ『杖を持つ老人』1882年9-11月、『杖を持つ老人』1882年11月6-8日
同じ題材、モデル。画家の成長がうかがえる。
そう、迷いがあるのだ。筆跡に。
展示番号25: フィンセント・ファン・ゴッホ『防水帽を被ったあごひげの漁師』
1883年、1月の作品。刻まれたモノ、生命の証明、それを繊細に、ただ、帽子と頭部のバランスが全く確立されていない。
展示番号26: フィンセント・ファン・ゴッホ『鳥に餌をやる女』
画家の技術が向上している。特に腕の描写は模写として既に完成の段階である。1883年4月・5月。
展示番号79: フィンセント・ファン・ゴッホ『灰色のフェルト帽の自画像』
自画像。輪郭の消失は、新印象派を想起させる。帽子がオシャレである。いや、言葉が出てこない。色彩、画家の到達点。研究。絵画の中の画家は、こちら(=鑑賞者側)を見ているようで見ていない。目の焦点は消失している。(目の焦点は、)すべてが色彩のみで構成され、つまり輪郭と同じだが、形がないのである。
画家はどこを見ているのか。彼は眉毛が薄いのか。
色彩で以て輪郭を表現するため、特に服と背景の、〈服の青の部分に背景の白が、白の部分に背景の青が使用されている、反転している〉
画家は、真実を捉えるために何をすべきか知っていた。つまり、人間こそ真実なのだ。そして。人間の真実を捉えるためにするべきことも知っていた。それは、自己を捉えることである。そして画家は画家の使命で以て、つまり色彩のみによって、これを完遂した。
展示番号89・90: フィンセント・ファン・ゴッホ『アルルの寝室』『ゴーギャンの帽子』
輪郭が回復する。〈線〉、つまり、原始的な絵画技法への回帰、ただし、床の色彩などに色彩遣いの熟練が〈ある〉。意図されたものかは分からないが、絵具の質感が残されており、これがまた単一の色彩の中に無限を生む。
展示番号88: フィンセント・ファン・ゴッホ『緑の葡萄畑』
良い。画家は輪郭を描いても良いし、描かなくても良いのだ。絵具の質感をキャンバスに残すこと、それを描写の技法とすること。
真実としての人間を捉える手段が、絵画
展示番号79を鑑賞した際に〈感じた〉通り、画家は自己にとっての真実を、すなわち〈人間〉を捉えようとしていたのではなかろうか。そして、彼にとって自己にとっての真実としての人間を捉える手段が、絵画だったのである。では、人間を絵画で捉えるためにはどうすれば良いのか。それは自画像を描くことである。〈私〉にとってもっとも身近な存在者である〈私〉を描くことで、彼は真実に近づこうとしたのではないか。だとすると、これはまた彼にとっての絵画に於ける最大の成功であると同時に、最大の失敗である。私たちとって、〈私〉にとって最も身近な存在者は〈私〉ではない。それによって初めて〈私〉を〈私〉として捉えることができる対象はまた、〈他者〉でもない。〈私〉や〈他者〉という考え方は、〈私 – と – 他者〉を〈同時に〉経験するその場に於いて副次的に派生するはずである。すなわち、〈私〉に固執し続けていたのでは、決して〈真実を捉えること〉=〈描くこと〉はできないのである。しかし同時に、あまりに〈私〉に固執し続けたために、画家は鑑賞者に対し、画家という人間の暴露された姿 = 真実を見せつけることになったのもまた、事実であろう。