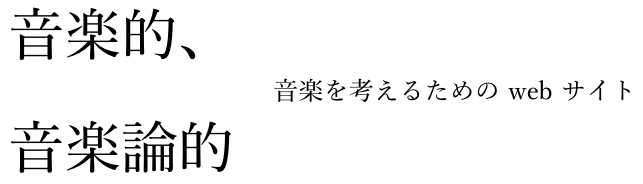X(旧Twitter) で、酩酊状態でさささっとポストした内容に、菊地成孔さん(以下、直接の知り合いでもないのに「さん」付けはなれなれしいかな、と思い、菊地氏と表記します)からリプライをいただきました。
続きを読む「 音楽理論 」一覧
Dilla Beat(Drunk Beat)理論化の歴史: グルーヴ感覚から数値へ

最近、Dilla っぽい Beat の作り方を教える機会がありまして、ただ、その作り方というのも、自分が 2012 年頃だか 2013 年頃だかにちょろっと小耳に挟んだものを、ずっと「そういうもんなんだな」と思って実践している内容で、それが本当に理論的に大勢の支持を得ているのかどうか、というのが、自分のなかでは疑問でした。
続きを読むスペクトル・モルフォロジー: 現代音楽における音楽理論の「別の仕方」

現代の音楽作品は、従来の和声やメロディーだけでなく、音色やテクスチャー、空間といった要素が作品の重要な構成要素として用いられています。特に、音楽の「色」や「形」をどのように捉え、分析するかは、作品を理解する上で欠かせない問題となっています。しかし、伝統的な音楽理論ではこれらの要素を十分に扱うことができず、新しいアプローチが求められているのです。それでは、「音の生命をどのようにつかむのか」という疑問に、どのように応えることができるでしょうか?
続きを読むアニメと音楽の交差点: リズム的同期の秘密を探る

アニメーション映画やマルチメディアでは、音楽と映像のリズム的な相互作用がどのように視聴者の体験を形作るのでしょうか? このテーマは、一見するとアニメーションや映画を楽しむ上で自然に受け入れられているものかもしれません。しかし、その背後には複雑な理論と分析が存在し、それを理解することで、作品への新たな視点が開かれることでしょう。
続きを読む音楽の基礎を再考する: 音律論の新たな展開

音楽を構成する要素の中で、音律は特に基本的かつ不可欠なものです。しかし、現代の音楽理論はしばしば平均律の枠内で教えられ、その他の音律についての理解はあまり深くないのが現状です。音律論と音楽理論の交差点にはどのような意義が存在し、私たちは音楽をどのように理解し、感じるべきでしょうか?今回は、「音律論から見た音楽理論の問題点」という論文を基に、これらの問題を詳しく掘り下げていきます。
続きを読むデトロイトとJ Dillaの物語: 音楽が紡ぐ再生の希望

デトロイトという街が抱える苦難と再生、そしてそれを象徴するアーティストであるジェイ・ディラ(J Dilla)の物語。私たちはこれらの「Fragments(断片)」というテーマを通じて、街と人、そして音楽の繋がりに何を見出すことができるのでしょうか?
続きを読むグラスパー、ケンドリック・ラマー、ハイエイタス・カイヨーテ: Dilla Time の継承者たち

音楽の世界で、リズムがどのように進化し、次世代のアーティストへと受け継がれていくのか――この問いに、あなたはどのような答えを持っていますか?アメリカ・デトロイト出身の音楽プロデューサーでありビートメイカー、ジェイ・ディラ(J Dilla)は、その答えをリズムの中に刻み込み、音楽史に革新をもたらしました。
続きを読む「グルーヴの秘密」に迫る: J Dilla の音楽とミクロリズム

音楽を聴いていると、思わず身体が動き出すような「グルーヴ」を感じる瞬間があります。それは一体どのようにして生まれるのでしょうか?また、あるリズムが「気持ち良い」と感じる背景には、どのような音楽的、文化的な仕組みが隠されているのでしょうか?
続きを読むサンプラーが J Dilla の音楽性に与えた影響

音楽制作におけるサンプリングは、どのようにJ Dillaの革新的なスタイルを形作ったのでしょうか?『Dilla Time』「Sample Time」(2022)【Amazon】では、サンプリング文化の進化と、J Dillaの音楽的ルーツとしての役割が詳述されています。本記事では、この章をもとにJ Dillaの音楽的ルーツと彼のビートメイキング技術を解説します。
続きを読むJ Dilla の創造力を育んだ友人関係と初期の音楽体験

J Dillaが世界に影響を与えるビートメイカーになるまで、どのような経験を積み重ねてきたのでしょうか? Dan Charnas 『Dilla Time』「Dee Jay」(2022)【Amazon】では、彼の若い頃の音楽的成長や初期の制作手法、友情を通じた学びが詳述されています。本記事では、「Dee Jay」をもとに、J Dillaの音楽的ルーツを探ります。
続きを読む