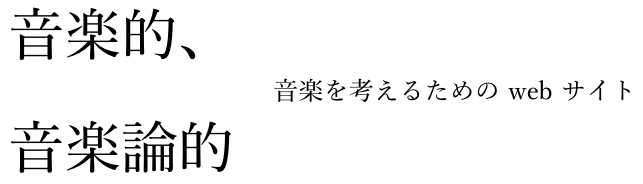金澤正剛『新版 古楽のすすめ』(2010年、音楽之友社)を読みながら、古楽について学んでいるところです。なお引用文は、特に断りのない限り、同書からになります。古楽については、以下を参考にしてください。
さて、第十二章では、古楽における即興演奏がテーマなのですが、これに関連して、楽譜と演奏の関係性のようなものが、ロココ音楽を例に説明されています。金澤正剛が、18世紀の代表的なクラウザン演奏家であるフランソワ・クープランの出版した教則本、『クラウザン奏法』を引用している部分を引用してみましょう。
記譜が正確ではないからと言って、当時のイタリア音楽の方がフランス音楽よりも優れているとは判断できないでしょう。そもそも音楽の客観的な優劣を判断することなどできるのでしょうか。
少し話が逸れそうなので、金澤正剛がさらに具体的に例を出して、楽譜と演奏の関係性について説明している部分を読みましょう。
シャルパンティエとは、マルカントワーヌ・シャルパンティエのことで、17世紀のフランスで活躍したロココ音楽の代表者の1人です。シャルンパティエの時代のフランス音楽(= ロココ音楽)を演奏する際には、「イネガル」という技法を用いなければ、当時の音楽 ら し さ を表現できないと言われています(えー、参考動画に「イネガル」という奏法が使われているかどうかは知りません!)。その「らしさ」を確認する方法はありませんが、「らしさを表現」するための「イネガル」のリズムが、金澤正剛によると「付点音符とも三連音符ともつかないあいまいなリズム」だったのではないか、ということです。
大げさに言えば、楽譜は音楽を殺すのではないでしょうか。楽譜は音楽を残すという点では非常にわれわれは恩恵を受けていますが、その楽譜から音楽を生むためには、楽譜によって殺された、点と点を結ぶ線を、演奏家自身が奏でださなければなりません。そしてこういった能力こそ、楽譜を演奏する分野の音楽において、最も重要だと思われます。