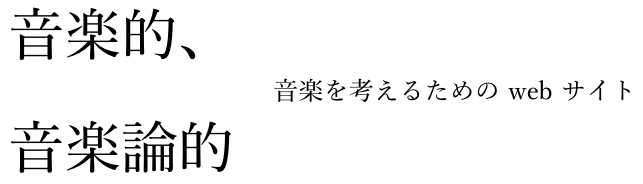金澤正剛『新版 古楽のすすめ』(2010年、音楽之友社)を読みながら、古楽について学んでいるところです。当エントリーは、「第十二章 即興演奏について」についてのノートになります。第十二章については、以下も参考にしてください。
なお引用文は、特に断りのない限り、同書からになります。
さて、第十二章では、古楽における即興演奏をテーマに、楽譜と演奏との関連性が説明されています。当時のヨーロッパ音楽は、現在コンサートホールで演奏されるようないわゆる「クラシック」とは異なり、楽譜に対してかなり寛容的だったようです。しかしその分、現在以上に楽譜リテラシーのようなものが求められていたのかもしれません。
少し引用してみます。
いやー、これですね、『~ 古楽のすすめ』には実際の譜例が載っていまして。同じ楽曲の一部分のが2つ。何故2つなのかというと、一方は「楽譜」、つまり(おそらく)出版された際に印刷された楽譜で、他方が「演奏」となっています。これはどういうことなのかというと、残された楽譜にはこのように書いてあるのだけれども、実際の演奏はこうしないと当時 ら し さ を表現できませんよ、ということです。
すごいっすね。とにかく楽譜というものがかなり優位を持っている(こういう言い方はしたくないのですが)近代産業社会における音楽に慣れ親しんでいる者にとってみると、相当の衝撃です。もうね、その通りに書けよ! とツッコミたくなります。しかしその通りには書かずに、代わりに「序文において説明」されている。何だそれは(笑)
こう推測することができるのではないでしょうか。つまり、17~18世紀の音楽家にとって、先ず音楽を演奏することが音楽行為において最優先であって(いや、これは現代でも当然と言えば当然なのですが(笑) ともすると忘れてしまいがちです)、記譜は二の次であった。そしておそらく・・・、楽譜はやはり音楽ではないし、音楽を紙に音楽とは別の表現であるところの記号で以って再現することは、はっきり言って難しい。ですので・・・、記譜はそこそこに、「ここはこう言ったノリで演奏してね!」というのを、(音楽に特化しない記号としての)言葉で説明した方が、はるかに音楽行為において有用であった。
最後に、金澤正剛の挙げている17~18世紀の曲集の例を引用しましょう。
そうなんですよね、楽譜を持ち寄って単に演奏するのではなくて、ちゃんとその楽譜や音楽を言葉で説明した方が、良い演奏になるはずなんですよね。私もロックバンドをしている(いきなり話が下世話になりましたが(笑))者として、身の引き締まる思いです。