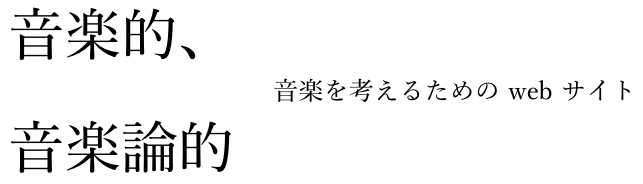「そりゃだって、地震が起こっても津波が起こっても、芸術が変わったというためしはないですよ。津波でいえば、スマトラ島の大津波があったでしょ。あれでなにかありました? 新しい芸術、ないでしょ。それはありえることではないんですよ。ポルトガルで一八世紀に大地震があった。ヴォルテールが書いているのは、いかに悲惨だったかということで、それと思想はなにも関係がない。それはレポートなんです。だから、ここでみんながそのことを問題にしても、現実に震災にあった人は誰も救われない。それは政治の問題なんですけど、いかにみんなががんばっていたかということを強調するだけ。そういうことで新しいものが生まれようがない。そういうことを言えば、メディアでバッシングされる。そういう国が日本なんですよ。だから新しいことはここでは起こらない。ただ、みんながそれについてひとこと言って、原稿料をもらうということです」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(2011)『アルテス Vol.01』p. 112)
インタビューのタイトル「問いかけながら道をいく — 今までの音楽は変わる時期にきている」を見て、その直後のこの冒頭の発言を読むと、非常に痛快な気分になる。そして何よりも・・・、あまりにも真実らしすぎて、胸が痛む。
アーティストがなんとか言って変わるようなことではない
「便乗。それで、便乗して現地に行く人もいる。それは善意なんでしょう。そういうことが報道されて、それで実際に政治でやっていることがごまかされたりする。内閣も変わったし、これからどうやって原発をまたやろうかという話になっていくと思うんですよね。だからそれはまたそういうふうに進んでいくだろうし、そういうことは少しずつ変わるかもしれないけれど、それはアーティストがなんとか言って変わるようなことではないんですよ。言論が変えることでもないです」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(2011)『アルテス Vol.01』p. 112)
「たとえば、エジプトでなにか起こるとわーっとなって、なにかが変わる。そういうことは日本ではありえないですよ。この前[九月一一日]のデモで一〇人くらい捕まったのかな。それで、それは終わりなんです。またもう一回やり直さなきゃならない。だから、継続するものは何もない」(同書 p. 112 – 113)
「昔からそうなんだけど、みんな職業があるでしょ。だから、日曜日にデモをやるでしょ。それじゃあ、だめなんですよ。職場を放棄して、わーっといく、そういうことが起こらないとなにもかわらないんです。サラリーマンのレジャーにすぎないわけ」(同書 p. 113)
「戦後ちょっとくらいかな。「血のメーデー」[一九五二年五月一日]っていうのがあるでしょ。皇居前でふたりくらい死んだ。警察隊に射殺されたわけですよ。そのときはアメリカ軍がバックにいたわけだけど、まあ、そこまでですね。日本共産党が非合法化されて、地下に潜ったわけ。そこで終わりですね」(同書、同ページ)
巻末の大友良英を除けば、これが『アルテス』創刊号の特集である「3. 11 と音楽」の最後のテキストになるのだが。今までの議論を全て破壊するような、あまりにも真実。最後の一言がさらに衝撃を与える。
「そこで終わりですね」
だから、音楽は必要じゃないんですよ
インタビュアーによる高橋悠治への、東日本大震災後に感受性が変わったか、という質問に対する答えとして、
「ないですね」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(2011)『アルテス Vol.01』p. 113)
「そういう人〔引用者注 「音楽を聴けなくなった人」〕はいますよね。だから、音楽は必要じゃないんですよ。それは最初からわかっていることでしょ。なぜ必要ないことをやっているのかというと、うーん、なぜだろうな。いろんな理由がありえるわけですよ。だけど、音楽をやっていれば世界が変わるっていうことはないでしょ」(同書、同ページ)
「必要じゃなければやってはいけないという思想があるんですよ。それが資本主義」(同書、p. 113 -114)
「ないですね」、という一言が非常に衝撃的だ。あまりにも正直過ぎる。だからこそ、高橋悠治のテキストを読みたくなる。また、「必要でなければやってはいけない」というのは、カネを儲けていなければ音楽ではない、に言い換えられるだろう。資本主義においては、私のような人間は音楽をしていないに等しいのだろう。
市民運動なんて贅沢にすぎない
「水牛楽団をやっていた頃は、市民運動みたいなことをやっていたわけだし、日本だけではなく、東南アジアと繋がっていた。ああいうところではたしかにあるとき、ある力を持つんですよ。それはいつもではないけれど。だけど日本ではそれは無理だ」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(2011)『アルテス Vol.01』p. 114)
「だいたい八〇年代には市民運動が壊滅していたから。〔中略〕日本ではみんなお金があって食べられるわけですよ。タイじゃ食べられない。食べられなきゃなんとかしなければならないでしょ。少しでも変えなきゃと。日本では自分たちは給料もらってボーナスもらってるんだから、別にそれでいいわけですよ。運動なんて贅沢にすぎないわけ」(同書、同ページ)
「運動なんて贅沢にすぎない」というのは、ただの印象でしかないが、東日本大震災以降の原発反対デモを見ていたら納得できよう。またこれは、震災以降よく見受けられた〈何かできることはないか〉という被災地以外の日本人の発言への私の不信感の理由であるのかもしれない。
ただ後半の、「日本では自分たちは給料もらってボーナスもらって」というところは、現代日本においては少しずつ高橋悠治の認識している事実と異なってきているのではないか。それでも、「運動なんて贅沢にすぎない」という考えは現代日本では変わらないだろうが。
震災によって何が変わるんですか
何が変わるのか、全部無駄ではないのか、ということについて。
「震災によって何が変わるんですか。みんなお金もらったほうがうれしいでしょ? 震災っていうのは、みんなお金がなくなる。いや、みんなお金がなくなるならいいんですよ。企業は儲けている。東電を見てごらんなさい。増税しても、電気代を上げても、会社は存続するでしょ。日本がいまやっていることは、いかに企業を救うかということなんですよ。だから、そういうところで雑誌にいろんなことを書いたって、全部無駄なんですよ。なにごとも時期というものがあるんです。条件もある。条件のないところでいくらやったって、それはヒロイズムなんです。そういうことをさんざんやってきた。左翼はとくに。「がんばるぞ」とか、そういうような歌さえあったし。だけど、その「がんばるぞ」というのがいまは権力の側に取られてしまった。いま、日本じゅうがひとつになって「がんばるぞ」となる。あれは五〇年前の左翼のスローガンだったんですよ。そのときは労働者が一体になって「がんばるぞ」となっていたのが、いまは日本国民がひとつになって「がんばるぞ」と言っているわけです。そういうことはそんなに簡単に変わらないです」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(2011)『アルテス Vol.01』p. 114 – 115)
これ以上、これに付け加えるべきことばはあるまい。
東日本大震災後に求められる音楽の方向性
インタビュアーの、東日本大震災が起きた後に求められる音楽の方向性はあるか、という質問に対して、
「地震が起こったからって、そんなこと思いつくわけないでしょ。でも、いままであった音楽というものが変わる時期にきているとは思っていますよ。それは地震とも原発とも直接は関係ない。二〇〇年くらいの近代主義とか啓蒙主義がもうどうにもならないところへ来ている。だから音楽もそういうものの影響を受けている」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(2011)『アルテス Vol.01』p. 115)
この発言が元になって、このインタビューの題名が決まっているのだが、「音楽は変わる時期にきている」と言ってもそれは、震災とは全く関係ないということに、留意せねばなるまい。高橋悠治は、もっと長期的な視点(= 歴史的な? 視点)で、音楽を捉えようとしているのだ。
なお、この発言の直後に「近代」的な音楽の例として、ベートーヴェンが挙げられている。
繰り返すが、このインタビューの引用元である『アルテス』創刊号の特集は、「3. 11 と音楽」である。とにかく高橋悠治は、このインタビュー以前のページのインタビューや論文、討論などをすべて否定するかのような発言をしているのだ。
即興なんて「みんなでがんばろう」のヴァリエーション
「いろんなジャンルからきて一緒に即興をやる。それも「みんなでがんばろう」のヴァリエーション」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(2011)『アルテス Vol.01』p. 116)
この発言は、変 わ っ た あ と の 音 楽 として「即興演奏家」が挙げられるのではないか、というインタビュアーの発言に対し、「「みんなでがんばろう」のヴァリエーション」と断言することで、けっきょく「即興」も「近代主義とか啓蒙主義」から生まれたものでしかない、ことを意図しているのだろう。
「この人はこういうスタイルでやってきた。そのスタイル、商品を寄せ集めてサラダのようにすれば、多様になるという発想でしょ。それではできないですよ」(同書、同ページ)
「スタイルというのは商品ですからね。だからいかにスタイルから逃れるかということでしょ。〔中略〕スタイルとか個性とかそういうものにとらわれるのはもう、それが近代なんです。即興的な方法でなにかできるとは思わないですね」(同書、同ページ)
「どうにもならなくなっている」音楽を変えるためには、「スタイルから逃れる」ことが必要である。しかし...、こういった発想もけっきょくは、近代的・資本主義的な経緯から発生するのではないか。
高橋悠治は極度に潔癖性のように思えるのだが、近代を通り過ぎた現代において、完全に近代から脱出することは不可能なのではないか。
練習について
「練習があれば本番があるでしょ。だからそういう考え方がもうおかしい」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(2011)『アルテス Vol.01』p. 116)
「よくいわれることだけど、練習は本番のように、本番は練習のように」ということがありますね。「練習は本番のように」ということは、たとえばあるフレーズを一回弾くでしょ。二回目には違うふうに弾かなきゃいけない。それが本番のように弾くということ。〔中略〕練習というのは “practice” 、「実践」でしょ。それは一回限りということですよ。反復練習というのは近代以降のものなんです。「本番は練習のように」ということは、家でやるようにくつろいでやるということです。ステージがあってそこから見下ろしてメッセージを出すんじゃなくて、自分で好きなことをやってそれを見にくる人がいるということです」(同書、p. 116 – 117)
これを読んだとき、かつて Youtube で観た高橋悠治の演奏する Xenakis 〈 Herma 〉の動画を思い出した。というのも、この動画には高橋悠治のインタビューも含まれているのだが、そのなかで 毎 日 練 習 す る こ と に似たような発言をしていたと記憶しているからだ。かつての発言と矛盾しないだろうか(この「矛盾」を排斥することも、近代の産物であるから、矛盾を排斥する必要はない、と返されたら、何も言えなくなるのだが(笑))。
いま確認すると、「毎日」とは言っていないが、「練習」とは言っている。しかし久しぶりにこの動画を観たが、過去の発言の揚げ足取りが無駄なほど、ヤヴァイ。
———、毎 日 練 習 す る こ と というのは、毎 日 実 践 す る こ と という意味なのかもしれない。例えば私は、ギターを弾く。同じフレーズを反復練習する。しかしその1回1回において音楽が奏でられている。そしてそれは音楽である以上、実践である。だから練習というのは言葉だけであって、実際には練習というのは存在しない、ということなのかもしれない。
そう言えば…、画家の「習作」というのが、歴史的なそれになれば 美 術 品 として市場から価値を認められる、これと同じなのかもしれない。音楽にも、ア ウ ト テ イ ク 集 という名の 商 品 が存在するではないか。
音楽を変えるためには、近代・啓蒙主義・資本主義といった現代の風潮から脱出せねばならない
「だからね、われわれの言葉はすでに資本主義化しているんですよ。どうしても力とか利益とか方法とか理想とかいわなきゃ話にならないでしょ。だから言葉から変えていかなきゃならないと思うけどね。でもそれはなかなか難しいです」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(同書、p. 117)
「どうにもならなくなっている」音楽を変えるためには、近代・啓蒙主義・資本主義といった現代の風潮から脱出せねばならないが、しかし脱出するための言葉も、近代・啓蒙主義・資本主義的な性質を帯びている。「練習」という言葉も、そのうちの一つだろう。だから「難しい」
大里俊晴と「役立たず」について。
引用元インタビューにおける一連の高橋悠治の発言によって、インタビュアーが大里俊晴追悼文集『役立たずの彼方に』を思い出したと発言したことを受けて、
「大里さんは役に立つことはなにもしなかった。ブラブラしてつっかけ履いて、一張羅で大学のキャンパスをうろうろしてみんなに愛されてた。その周りにある空間が漂っているわけですよ。それがだいじなことでね。それを役に立つか立たないかと定義しちゃうとすごく狭くなっちゃう」(同書、p. 118)
渋谷望、「素人の乱」などについて
「渋谷望さん[社会学者。著書に『魂の労働』『ミドルクラスを問い直す』など]のような理論家がいる。それから高円寺でやっているような人たち[松本哉が経営するリサイクルショップ「素人の乱」を中心に展開されている社会運動]も、そこらへんとある繋がりがある。そういう表面にはあまり出て来ないけれど、流れているものがあるんですよ。そっちのほうがだいじなんだけれど、それはあまり表に出すと買収されちゃう。だからあるところで留まっていなければならない」(同書、p. 119 – 120)
隙間、説明できない、矛盾、不完全について
「(話を)きちんとまとめるというその態度、それが体制だと思う。全部綻びてないといけない。そんなに生前と隅から隅へと矛盾のないものが権力を取ったらどうなりますか? それはすごく危険なこと。だから隙間だらけで、説明がつかないことがいっぱいあって、矛盾だらけで、不完全である。それだから違うふうになっていくでしょ」(高橋悠治「問いかけながら道をいく ——— 今までの音楽は変わる時期にきている」(2011)『アルテス Vol.01』p. 120)
「完全なことがいいということは、神がいちばんだということでしょ。それは間違っているんですよ」(同書、同ページ)
この最後の「神」に対する発言だけ、同意できない。「神」は「いちばん」であり「完全」だが、人間が自らをそれと同一化することを目標とできるような「完全」ではない。「神」が「完全」であるからこそ、人間は「隙間だらけで、説明がつかないことがいっぱいあって、矛盾だらけで、不完全」なのである。だから、「神」と 人 間 が 「綻びていないといけない」ことは、両立する。