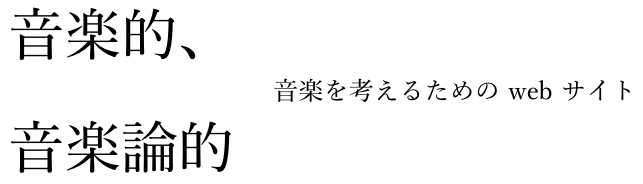音楽の 現 象 学 というタイトルに偽りない、中身の濃い、私の読んできた中で最も音楽の本質を衝いている本のうちの1つです。ページ数が短いからと言って、しかもその1/3程度がコンサート記録や、誰 得 の セ ル ジ ュ お じ い ち ゃ ん モ ノ ク ロ グ ラ ビ ア (本当に誰が得するんだよ! 要らねえよ! 本の値段高くするために無駄なページ作ってんじゃねえよ!)であるからと言って、侮ることはできません。チェリビダッケの一言一言は、膨大な注釈が必要でしょう。つまり、チェリビダッケが何を言おうとしているのかを、単語ごとに、文節ごとに、文ごとに・・・、確認しながら読まなければなりません(つまり、かなり読み難い。これは翻訳にも原因があるのかもしれません)。
さて、なぜ「現象学」なのでしょうか。そもそも音楽の「現象学」は可能なのでしょうか。音 楽 そ の も の から、音 楽 全 体 と は 何 か を 問 う ことは可能なのでしょうか。最初は疑っていましたが、「響き」(「響き」については詳しくは後述します)と「テンポ」の説明の箇所である、
「ということは時間的な次元は最初から音程の中に含まれているということですよ」(セルジュ・チェリビダッケ著 石原良也・鬼頭容子訳『音楽の現象学』2006、アルファベータ p. 46)
そしてこの音楽の現象学は、私が最近、音楽に対して持っているある考えに確信への後押しをしてくれた、このような気がします。その考えとは、
音楽は或る音現象に対する自己(≒人間)の精神作用である。
というものです(そしてこのような考え方を持ってしまっているゆえに残念ながら、『音楽の現象学』を(も?)自分の考えに即してしか読むことができませんでした)。
私の言う場合の「或る音現象」とは、チェリビダッケの言葉では「響き」になるのかもしれません。
ただ、私も最初誤解していましたが、「響き」というのは或る程度日常的に使われている単語です。なので、「響き」という単語で以って連想する意味内容は、かなり人それぞれかもしれません。しかしチェリビダッケは、「響き」を日常的な意味よりもっと———、こう言ってよければ 本 質 的 な 、あるいは、厳密な、もしくは、広い意味で使用しています。音の鳴っている状況全般とまでは言わずとも、それに近い意味で使っていると言ってもいいかもしれません。
では、「響き」によって音楽はどのように説明されるのでしょうか。チェリビダッケの言葉の引用をしましょう。
「音楽は、今在るなにものかではないのです。唯一無二の条件のもとで、何かが音楽に成り得るのです。そして、この何かとは、響きです。つまり、響きは音楽ではないが、響きは音楽に成り得るのです」(同書 p. 18)
音楽とは何か、という問いに対し、チェリビダッケは「分からない」と答えます。しかし、何が音楽に成り得るのか、という問いに対しては、「響きである」と答えるのです。そして、
「音楽の本質は、音 – 人間の関係に、この時間的な響きの構造と人間的な心の構造の合致するところにあるのです」(同 p. 23)
と述べます。
このことから分かるのは、音楽がそれ自体として存在するのでは決してなく、人間が「響き」に対して何らかの働きをすることによって音楽を音楽たらしめている、ということではないでしょうか。
というこは・・・、上述の私の音楽テーゼは、確信へと近づきつつもしかし同時に、次のように言い換えられなければならないでしょう。
つまり、音楽は、ある音現象と、自己(≒ 人間)の精神作用との相互影響 関 係 である、と。
相変わらず脈略もなく音楽関係の本を乱読しています(「脈略なく」「乱読」するとは何という重言でしょうか!)。
きっかけはキェルケゴール『キリスト教の修練』でした。
『キリスト教の修練』では、キリスト教芸術が「讃美」であるとして否定されます。新のキリスト者であれば、キリストを「讃美」せずに、「追従」、すなわち、キリストの行ったように自らも実践しなければならない、ということです。これを読んだとき、好きなヒトから、自分の好きなコトを否定されたような、かなり悲しい気持ちになりました。では 音 楽 を 含 め た 芸術とは何なのでしょうか、音楽とは何なのでしょうか。キェルケゴールの言うように、人間は信仰するべきであるなら、人間には音楽を含めた芸術は必要ないのでしょうか。あるいは、「追従」するような「芸術」は可能なのでしょうか。
以上の問いへのヒントを探すために、クリストファー・スモール『ミュージッキング』、田村和紀夫『音楽とは何か』の脈略のない乱読をしました。しかしヒントはありませんでした。そして、チェリビダッケ『音楽の現象学』にも。
ただ、田村和紀夫を除く(笑)2冊の本によって、「音楽とは何か」という問いへの回答の道筋がかなり・はっきりと示された気がします。両書とも、ツッコミどころはあるにせよ、(片方は音楽それ自体を否定していますが)音楽それ自体の内部に留まろうとしつつ、音楽とは何かを深く考えさせてくれます。