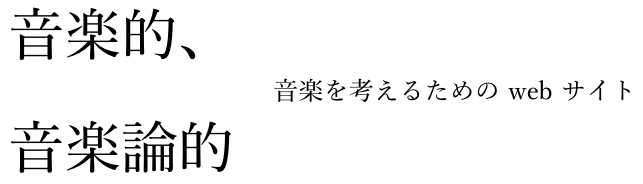音楽を「聴く」という行為は、私たちにどのような知識や感覚をもたらすのでしょうか? また、それを「分析」することで、作曲者の意図や楽曲の構造をより深く理解することができるのでしょうか?これらの問いは、音楽愛好家だけでなく、音楽学者や哲学者にとっても長年のテーマとなってきました。
ユリア・クーゼル(Julia Kursell)「Contesting the Musical Ear: Hermann von Helmholtz, Gottfried Weber and Carl Stumpf Analyzing Mozart」(2024、邦題「音楽的耳の再考: ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ、ゴットフリート・ウェーバー、カール・シュトゥンプフによるモーツァルトの分析」)によれば、音楽分析が19世紀後半に一つの独立した分野として確立された背景には、音楽を「聴く」ことと「分析する」ことの関係が深く影響を与えているといいます。この論文では、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツ(Hermann von Helmholtz)、ゴットフリート・ウェーバー(Gottfried Weber)、カール・シュトゥンプフ(Carl Stumpf)の3人がモーツァルトの楽曲をいかに分析し、それが音楽学の進化にどのような影響を与えたかを具体例とともに解説しています。
音楽分析は、もともと作曲家の教育や音楽理論の理解を助けるために発展しましたが、次第にリスナーが楽曲をより深く味わうための手段としても重要視されるようになりました。例えば、ヘルムホルツは、モーツァルトの《アヴェ・ヴェルム・コルプス》(Ave verum corpus, K. 618)を用い、音響学と音楽理論の架け橋として調和性を測定しました。一方、ウェーバーは、モーツァルトの《弦楽四重奏曲 ハ長調》(K. 465)を分析し、リスナーが楽曲の不協和音をどう受け止めるかに注目しました。シュトゥンプフは、音響心理学の観点から、モーツァルトの《セレナード 変ロ長調》(K. 361)を分析し、聴覚体験の構造を探りました。
今回の記事では、この論文の内容を紹介しながら、音楽分析という行為がいかにして19世紀から現代まで発展してきたかを解説していきます。
音楽分析の起源と19世紀の背景
クーゼルによれば、音楽分析が今日のように独立した学問分野として発展する以前、その役割は主に作曲技法の学習や音楽教育に限定されていました。しかし、19世紀になると、社会的背景の変化や新たな科学技術の進展により、音楽を「分析する」という行為がそれ自体で重要性を持つようになります。この変化の鍵となったのが、音楽を「聴く」ことと「作る」ことを分離し、リスナーとしての視点を重視するアプローチの台頭でした。
音楽分析の歴史的背景
19世紀は、産業革命とともにブルジョア階級が台頭し、音楽を楽しむ場としてのコンサート文化が発展した時代でもありました。これにより、音楽は作曲家や演奏家だけのものではなく、広く一般市民が「聴く」対象として消費されるようになりました。この変化に伴い、音楽の「聴き方」を教えるための理論や解釈が求められるようになり、音楽分析がその需要を満たす役割を担ったのです。
さらに、当時の学術的潮流として、自然科学や実証主義の影響を受けた研究が進みました。特に、ヘルムホルツのような科学者は、音楽を物理学や生理学の視点から研究し、新しい方法論を導入しました。このような取り組みによって、音楽分析は科学的探究の対象としての位置づけを獲得していきます。
分析の視点を変えた3人の研究者
「Contesting the Musical Ear: Hermann von Helmholtz, Gottfried Weber and Carl Stumpf Analyzing Mozart」が取り上げるヘルムホルツ、ウェーバー、シュトゥンプフの3人は、それぞれ異なるアプローチで音楽分析を発展させました。
- ヘルムホルツは、音の物理的性質と聴覚の生理学を研究し、モーツァルトの楽曲を実験的に分析することで、和音の調和性や耳の反応を測定しました。
- ウェーバーは、モーツァルトの《弦楽四重奏曲 K. 465》を例に、リスナーがどのように楽曲を理解するかを重視し、聴覚的な体験を分析の中心に据えました。
- シュトゥンプフは、音の構造を解明する実験装置を開発し、音楽心理学の観点から音楽の知覚と分析を結びつけました。
音楽分析の独立とリスナーの登場
19世紀後半になると、音楽学が学問として確立され、音楽分析もこの枠組みの中で発展していきます。1885年に創刊されたドイツ語の学術雑誌『Vierteljahrsschrift für Musikwissenschaft』は、この動きを象徴する存在です。この時代の音楽分析は、作曲家の教育に限定されるものではなく、リスナーが楽曲をより深く楽しむための手段としても重視されるようになりました。
このように、音楽分析が19世紀においてどのような社会的背景と学術的変化の中で発展していったのかを理解することで、現代の私たちが音楽を「聴く」行為の背後にある歴史的な文脈を知ることができます。
では続いて、具体的な分析例として、ヘルムホルツの研究を取り上げます。彼がモーツァルトの楽曲をどのように分析し、それが音楽理論と科学を結びつけたかを見ていきましょう
ヘルムホルツの音響理論と《アヴェ・ヴェルム・コルプス》分析
音楽を「聴く」という行為に科学的なアプローチを持ち込んだ先駆者の一人が、ヘルマン・フォン・ヘルムホルツです。彼の著書『音の感覚に関する生理学的基礎』(On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music)は、音楽理論と聴覚の生理学を結びつけ、音響学の新たな可能性を開きました。この章では、ヘルムホルツがモーツァルトの《アヴェ・ヴェルム・コルプス》(Ave verum corpus, K. 618)をどのように分析したのかを見ていきます。
ヘルムホルツの音響理論と「共鳴理論」
ヘルムホルツは、音響学を基盤に「共鳴理論」を提唱しました。この理論では、内耳にある基底膜の微細な構造が特定の周波数に共鳴し、音を識別するとされています。この仮説は、音がどのように認識され、特定の調和や不協和として感知されるのかを説明するものでした。たとえば、彼は和音の調和性を「音波の干渉」によって説明し、同時に発生する周波数が耳にどのような影響を与えるのかを探りました。
《アヴェ・ヴェルム・コルプス》を用いた実験的分析
ヘルムホルツは、この理論を実験的に検証するためにモーツァルトの《アヴェ・ヴェルム・コルプス》を選びました。この楽曲は、その「清らかで滑らかな和音進行」で知られており、調和性の分析に適した例として注目されました。彼は以下のような手法で分析を行いました。
和音の分布を評価
楽曲の冒頭部分では、すべての和音が「完全に調和する」とされるポジションに配置されています。これにより、聴覚に非常に「心地よい」印象を与えることをヘルムホルツは確認しました。
調和性の変化を追跡
楽曲の中間部分に進むと、調和性が意図的に「曖昧で、神秘的」な印象に変化します。この部分では、不協和音や「望ましくないポジション」の和音が多く含まれており、聴覚に異なる効果を生み出していることが示されました。
結論部の再調和
最終的には、「完全に調和する」和音で締めくくられる構造を持つこの楽曲は、聴覚的な「カタルシス」を与えると結論付けられました。
科学と音楽の融合
ヘルムホルツのアプローチの革新性は、音楽の美しさや感情表現を単なる主観的な体験として扱うのではなく、科学的に解明しようと試みた点にあります。彼は、和音の調和性を示すチャートを作成し、各和音がどの程度「心地よい」かを数値的に評価しました。また、実験装置を使用して、モーツァルトの楽曲が理論的仮説と一致することを確認しました。
モーツァルトの「優れた耳」と科学の視点
ヘルムホルツの分析では、モーツァルトの「優れた耳」が特に重要視されています。モーツァルトが《アヴェ・ヴェルム・コルプス》で示した調和性は、単なる作曲技法ではなく、聴覚の限界を深く理解した上での芸術的な選択であると考えられました。彼の研究は、モーツァルトの楽曲を単に「美しい」と評価するだけでなく、その背後にある科学的構造を解き明かすことで、音楽の新たな理解を促しました。
では続いて、、ゴットフリート・ウェーバー(Gottfried Weber)がモーツァルトの《弦楽四重奏曲 ハ長調》(K. 465)をどのように分析し、リスナーの視点を重視したかを詳しく見ていきましょう。彼のアプローチは、ヘルムホルツとは異なる形で音楽分析の可能性を広げました。
ウェーバーによる《K.465》の分析: 作曲家と聴衆の間で
ウェーバーは、音楽分析におけるリスナーの視点を重視し、その発展に大きく寄与した人物です。彼はモーツァルトの《弦楽四重奏曲 ハ長調》(K. 465)を分析することで、音楽を「聴く」ことと「分析する」ことの間に新たな橋を架けました。この作品は、「不協和音四重奏曲」(Dissonanzenquartett)として知られ、その冒頭の大胆な不協和音で多くの論争を引き起こしました。ここでは、ウェーバーがどのようにこの楽曲を分析し、リスナーと作曲家の視点を結びつけたのかを詳しく見ていきます。
モーツァルトの《K. 465》とその独創性
モーツァルトの《K. 465》の冒頭は、非常に独特で「不協和音」とも形容される和声進行で始まります。通常、弦楽四重奏曲は明瞭な調性と調和の取れた音響を持つものですが、この楽曲はあえて「未導入の不協和音」や「誤った関連性」を含む大胆な手法を用いています。このような手法により、聴衆は最初に強い不安感を覚える一方、その後の調和的な展開によって安堵と美しさを感じる構造となっています。
この冒頭部分は、楽譜が出版されて間もなく、ベルギーの音楽理論家フランソワ=ジョゼフ・フェティス(François-Joseph Fétis, 1784–1871)によって批判されました。彼はこれを「誤り」と呼び、修正案まで提示しました。一方で、ウェーバーはモーツァルトの意図を尊重し、この不協和音を受け入れるべき選択として捉えました。
ウェーバーの分析: 音楽の「聴き方」を教える試み
ウェーバーの《K. 465》の分析は、聴衆が楽曲をどのように受け取り、理解すべきかを提示することを目的としていました。彼はモーツァルトの冒頭の不協和音を単なる「誤り」として片付けるのではなく、以下のような観点から分析しました。
聴衆の耳と音楽理論の調和
ウェーバーは、聴衆がこの冒頭の不協和音をどのように受け取るかを中心に議論しました。彼は、音楽理論の規則に基づきながらも、リスナーがその規則にどのように反応するかを考慮しました。彼の目的は、モーツァルトの和声進行がリスナーに与える「効果」を説明することでした。
仮説的な選択肢の提示
ウェーバーはモーツァルトが選ばなかった和声進行の「仮説的な選択肢」を提示し、それを比較することでモーツァルトの選択の独自性を浮き彫りにしました。彼はリスナーに対し、「もし別の選択がされていたらどうだったか」を想像させ、音楽の可能性について考える機会を与えました。
リスナー教育としての分析
ウェーバーは、自身の分析を通じて聴衆が音楽をより深く理解できるよう導きました。彼は楽譜や和声進行の詳細な解説を行いながら、聴衆が自ら楽譜を追い、ピアノで再現することを推奨しました。このような「聴くための分析」というアプローチは、19世紀の音楽分析において革新的なものでした。
フェティスとの対比: 作曲家の意図を尊重する視点
フェティスは、モーツァルトの不協和音を修正すべきものと捉え、自ら「正しい」和声進行を提案しました。一方、ウェーバーはこのような修正案を否定し、不協和音をモーツァルトの意図的な選択と解釈しました。彼にとって重要だったのは、作曲家が意図した音楽的効果をリスナーがどのように感じ、理解するかという点でした。
リスナーの視点を取り入れた分析の意義
ウェーバーの分析は、単に作曲技法を解説するものではなく、リスナーが音楽をより深く楽しむためのガイドとして機能しました。このアプローチは、19世紀の音楽分析において革新的なものだっただけでなく、現代における音楽理論や解釈学にも通じる視点を提供しています。
では続いて、シュトゥンプフが音響心理学と実験的手法を用いてモーツァルトの《セレナード K. 361》を分析した取り組みを取り上げます。シュトゥンプフは、科学的実験とリスナーの経験をどのように結びつけたのかを探求しました。
シュトゥンプフの実験装置とその音楽分析への応用
シュトゥンプフは、音響心理学の先駆者として、音楽と聴覚の科学的理解を大きく進展させた人物です。彼は音響の構造を解明するための独自の実験装置を開発し、その成果を音楽分析に応用しました。本章では、シュトゥンプフの研究がどのように行われたのか、そしてその成果がモーツァルトの《セレナード K. 361》(Gran Partita)の分析にどのように活用されたのかを解説します。
実験装置の概要: 干渉装置による音響分析
シュトゥンプフの実験研究は、干渉装置と呼ばれる特別な装置を中心に行われました。この装置は、音の周波数成分を取り除いたり、再構成したりすることで、音響の構造を詳細に分析するものでした。装置の仕組みは以下の通りです。
干渉による音成分の消去
管状の装置内に挿入された突起(スパイク)が特定の周波数を打ち消すことで、音からその成分を除去します。この操作により、音がどのような周波数成分で構成されているかを解析しました。
音の再構成
取り除いた周波数成分を段階的に戻しながら、元の音を再構成しました。これにより、音の各成分が全体の音響にどのように寄与しているのかを確かめることができました。
楽器音の分析
楽器の音がどのようなスペクトル(音響の周波数分布)を持つのかを調べ、音色や音の認識に影響を与える要素を解明しました。
音楽分析への応用: 《セレナード K. 361》の分析
シュトゥンプフは、この実験装置で得られた知見をもとに、モーツァルトの《セレナード K. 361》を分析しました。この作品は13の管楽器のために作曲されており、音色の多様性とアンサンブルのバランスが特徴です。シュトゥンプフは、以下のような視点からこの作品を分析しました。
管楽器の音色と周波数成分の関係
例えば、フレンチホルンの音が弱い音量で演奏された際、耳には音高が1オクターブ低く感じられる場合があることを指摘しました。これは、音色における特定の周波数成分が耳にどのように影響を与えるかを示しています。
音楽演奏における音響効果
シュトゥンプフは、モーツァルトの音楽における楽器間の音響的な相互作用を実験装置で再現しました。例えば、音色や倍音(基本周波数の整数倍の周波数成分)の変化が、楽曲全体の印象にどのような影響を与えるかを詳細に分析しました。
リスナーの経験と分析の結びつき
実験で得られたデータをもとに、シュトゥンプフはリスナーが音楽をどのように知覚し、理解するかを考察しました。彼は、科学的な音響分析が音楽の鑑賞体験をより深める手助けになることを示しています。
実験と経験の融合: 科学的分析の意義
シュトゥンプフの研究の重要な点は、科学的な実験結果をリスナーの主観的な体験と結びつけたことにあります。彼の分析では、リスナーが音楽をどのように「聴く」かが、科学的知見によってより深く説明されるとともに、音楽鑑賞の新たな視点が提供されました。
また、モーツァルトの《K. 361》を分析対象に選んだことは、この作品が持つ音色の多様性とアンサンブルの複雑性を科学的に理解しようとする試みでした。シュトゥンプフは、楽器音の特性や音色の変化が作品全体の「聴き心地」にどのように影響を与えるかを具体的に示しました。
音楽分析における科学と感性の統合
シュトゥンプフの研究は、音楽分析を科学的な実験と主観的な感性の双方に基づくものへと進化させました。彼のアプローチは、音楽理論の発展にとどまらず、音響心理学やリスニング体験の理解においても多大な影響を与えました。
ではつづいて、音楽分析が19世紀を通じてどのように変遷し、リスナーの体験をより重視する方向に進化したのか、「Contesting the Musical Ear」の考察を紹介します。シュトゥンプフ、ウェーバー、ヘルムホルツの研究がそれぞれどのように「聴く」ことを再定義したかを整理しましょう。
音楽分析の変遷: 分析からリスニングへ
19世紀の音楽分析は、作曲家の技法を解き明かすための手段として始まりましたが、次第にリスナーの体験を重視する方向へと進化しました。この変化は、単に音楽理論の発展にとどまらず、音楽の鑑賞や教育、さらには音楽文化全体に影響を与えました。本章では、19世紀後半における音楽分析の変遷を振り返り、分析からリスニングへとシフトしたプロセスを探ります。
分析の目的の変化: 「作る」から「聴く」へ
19世紀初頭、音楽分析は主に作曲家の教育を目的としていました。バロック期から古典派に至るまで、音楽の構造や和声の進行を分析することは、新たな作品を作り出すための規範を学ぶ手段とされていました。しかし、産業革命以降、コンサート文化が発展し、音楽は「聴衆のための芸術」として再定義されました。この変化に伴い、音楽分析の目的も、「作るため」から「聴くため」へとシフトしていきます。
例えば、ヘルムホルツは、音楽を「耳で感じる科学」として捉え、和音や調和性をリスナーがどのように受け取るかを探求しました。彼の研究は、音楽を生理学や物理学の観点から分析する新たな視点を提供しました。
リスナー中心の分析へ: ウェーバーの貢献
ウェーバーは、音楽分析においてリスナーの視点を取り入れた最初期の研究者の一人です。彼はモーツァルトの《弦楽四重奏曲 K. 465》を分析する際に、聴衆が楽曲の不協和音をどのように感じるかを中心に据えました。ウェーバーのアプローチは、リスナーが楽譜を通じて作曲家の意図を「理解する」だけでなく、音楽そのものを体験的に「感じる」ことの重要性を強調しました。
科学と感性の融合: シュトゥンプフの革新
シュトゥンプフは、音楽分析における科学と感性を結びつけた人物です。彼は実験装置を用いて、音響の物理的性質を分析すると同時に、リスナーがどのように音楽を知覚するかを探求しました。シュトゥンプフの研究は、音楽分析を単なる記号の解析から、リスニング体験を深めるための科学的手法へと拡張しました。
彼の研究により、音楽が持つ「音響的な美しさ」や「聴覚的快感」が、科学的に説明可能であることが示されました。これにより、音楽分析はリスナーの体験を中心としたものへと変容し、音楽理論と心理学の架け橋となりました。
音楽分析の進化とその意義
19世紀後半の音楽分析の変遷は、「音楽を聴く」という行為が、どのように知的探究の対象となったかを示しています。ヘルムホルツ、ウェーバー、シュトゥンプフのような研究者たちは、それぞれ異なるアプローチで音楽とリスニング体験を結びつけ、音楽理論をより豊かなものへと進化させました。
彼らの研究は、以下のような点で現代にも影響を与えています。
音楽教育の変革
音楽分析がリスニング体験を豊かにする手段として活用されることで、音楽教育がより体験的なものになりました。
鑑賞文化の発展
音楽を単に「演奏」や「作曲」するものではなく、「聴いて楽しむ」文化として広める一助となりました。
音楽心理学の基礎
音楽が聴覚に与える影響を科学的に研究する分野として、音楽心理学が確立されるきっかけを作りました。
では最後に、本記事のまとめとして、モーツァルトの楽曲が持つ音楽的価値と、それが現代の私たちに何を伝えているのかのクーゼルの考察を紹介します。音楽分析の視点を通して、モーツァルトの音楽がいかにして時代を超えて影響を与えているのかをみていきましょう。
モーツァルトの音楽が示すもの
モーツァルトの音楽が持つ普遍的な魅力は、単なる感覚的な美しさにとどまらず、その背後にある構造的、心理的な深みからも生じています。今回の記事では、19世紀における音楽分析の変遷を追いながら、ヘルムホルツ、ウェーバー、シュトゥンプフの3人の研究者がモーツァルトの楽曲を通じて示した音楽分析の可能性を探りました。最後に、モーツァルトの音楽が私たちに何を示しているのか、彼らの研究を振り返りながらクーゼルによる考察を紹介しましょう。
科学的視点から見たモーツァルトの音楽
ヘルムホルツは、音響学と生理学の視点から音楽を解明することで、モーツァルトの楽曲が持つ「調和性」を科学的に説明しました。《アヴェ・ヴェルム・コルプス》における調和的な和声進行は、単なる感覚的な快楽にとどまらず、物理的な音響特性によっても支持されていることを明らかにしました。彼の研究は、音楽が科学的な視点でも深く分析可能であることを示し、モーツァルトの作品が持つ構造的な精密さを証明しました。
リスナーの視点を取り入れた音楽の理解
ウェーバーは、音楽分析にリスナーの視点を導入することで、モーツァルトの楽曲の持つ感情的な力を説明しました。《弦楽四重奏曲 K. 465》における大胆な不協和音の使用は、単なる規則違反ではなく、聴衆に強い印象を与えるための計算された手法であると解釈されました。ウェーバーのアプローチは、作曲技法の分析だけでなく、リスナーがどのように音楽を体験し、感じるかを考察する新しい道を切り開きました。
心理学的分析による音楽体験の深化
シュトゥンプフは、音響心理学の観点から音楽を分析することで、モーツァルトの《セレナード K. 361》が持つ音色の豊かさとアンサンブルの巧妙さを解明しました。彼の研究は、音楽が聴覚的な体験としてどのように構成され、知覚されるのかを示し、音楽の分析がリスニング体験の向上に寄与する可能性を示唆しました。
モーツァルトの音楽が現代に伝えるもの
19世紀の音楽分析の研究者たちは、それぞれ異なる視点からモーツァルトの楽曲を探求しましたが、共通して示されたのは、音楽が単なる美的体験にとどまらず、知的、科学的、感情的な深みを持つ芸術であるという点です。彼らの研究は、モーツァルトの楽曲が時代を超えた価値を持つ理由を明らかにし、現代においてもその意義を再認識させるものとなっています。
モーツァルトの音楽は、分析を通じて構造的な精密さや心理的な深みを発見する喜びを提供し、同時に、それを「聴く」ことによって生まれる感動を与えてくれます。この両面を理解することで、音楽はより豊かなものとして私たちの生活に深く浸透するのです。