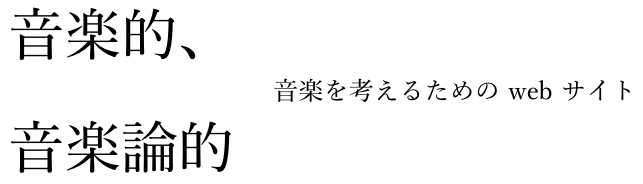X(旧Twitter) で、酩酊状態でさささっとポストした内容に、菊地成孔さん(以下、直接の知り合いでもないのに「さん」付けはなれなれしいかな、と思い、菊地氏と表記します)からリプライをいただきました。
菊地氏から返事をもらったということで、X 上でリプライして、なんかそこでごにょごにょ盛り上げるべきだったかもしれないのですが(先方の戦略的に。そして「senpou」と入力して変換キーを押したときに「旋法」が第一候補だった点で、わたしがかつていかに菊地ファンだったかということが思い出されてきたのですが(そしていまは卒業してしまっているのですが))、正直、議論の展開という点で、X は個人的に肌に合わず、ゆえにブログ記事を書いてその URL を送りつける、というプレ SNS な、所作を選ぶことにしました。
いや、プレ SNS でもないですね。
むしろ古き良き SNS 所作かもしれません。
さて、菊地成孔さんからリプライをいただいた、私の X 上のポストの要点はだいたい次の通りです。
最近、西田・中辻(編)『近代日本と西洋音楽理論』(2025)を読んだのですが、この第5章がとても面白く、西洋の音楽理論と東洋の音楽理論を統合しようとした箕作秋吉(1895-1971)という音楽家が取り上げられているのですが、秋吉の理論と、リディアン・クロマティック・コンセプトとの比較が論じられています。
私は、箕作はこの本で初めて知ったのですが、リディアン・クロマティック・コンセプト(以下、リディクロ)は菊地氏の著書『憂鬱と官能』だか『マイルス本』だか『東大アイラー』だかどれだったかで 15 年くらい前に知りました。とはいえ、そのリディアン・クロマティック・コンセプトの内容をしっかり理解しているわけではありません。菊地氏の著書でリディクロについての記述で印象的に覚えているのは、「リディアン・クロマッティック・コンセプトはカルト」という点です。なぜカルトなのかというと、その内容自体が非科学的で神秘主義的な側面があった、みたいなことが書かれていたかどうかは覚えていないのですが(そしていま、菊地氏の著書が手元にないので、確認しようもないのですが)、そういったことではなく、『リディアン・クロマティック・コンセプト』の教科書は 2 巻あって、1 巻目はふつうに買えるけど、2 冊目はセミナーみたいなのを受けないと入手できない、といったことが確かに、菊地氏の著書に書かれていたという記憶があり、要するにリディクロはその内容というよりも伝授の仕方に秘教的な側面があるからカルトと言える、と。
本当にそういうことが書いてあったかどうか、確かめようがないのが残念なのですが、そういうリディクロ = 秘教的 = カルト、マトモに研究している人などいない、という認識があったので、割と研究書よりである『近代日本と西洋音楽理論』でリディアン・クロマティック・コンセプトの名前を見つけたとき、たいへん意外でした。
まともな研究の対象だったのか、と。
『近代日本と西洋音楽理論』5 章を執筆した柿沼敏江は、京都市立芸術大学の名誉教授で、現代音楽に関する著書や翻訳を多く出版されているということで、リディクロがカルトかどうかの判断はいったんここでは保留にするにしても、「マトモに研究している人などいない」という私の認識は恥ずかしいほどの大間違いでした。
で、菊地氏の著書を読んで形成された記憶の中の「『リディアン・クロマティック・コンセプト』の教科書は 2 巻あって、1 巻目はふつうに買えるけど、2 冊目はセミナーみたいなのを受けないと入手できない」という情報も、どうやら柿沼の論稿によれば誤りで、まずリディクロの教科書は主要な版が 4 つあって(最終版は 2001 年。『憂鬱と官能』が出版されたのが 2004 年なので、『憂鬱と官能』執筆時に、リディクロ最終版が出版された、みたいな情報が日本に普及されていなかった可能性もありますね)、「第1巻」と題されている。のですが、第2巻は出版されませんでした。
レッスンを受けないと入手できないのは「教授資格」で、毎週 2 〜 3 時間のレッスンを 1 年間受けると、教授資格が与えられるそうです。
というのを知ると、自分の記憶のなかのリディクロ = カルトという印象とは違い、リディクロの内容うんぬんはいったん、不問にするにしても、教授資格を入手するのに1年間のレッスンを受けなければいけない、というので以って「カルト」というのは自分は、違うな、と思った次第です。
そういう意味で、X で、「菊地成孔の言っていることを間に受けて「リディクロはカルト」だと思い込んでいたが、そうとも言い切れないところはもある」とポストしたところ、菊地氏から「マジで?」的なリプライをいただいたのです。
同時に 3 つくらいリプライをいただいていて、私のいま運用しているアカウントはフォロワー 20 人の最弱アカウントなのですが(まともに伸ばす気ない)、いきなり通知が 3 つも来たので、けっこうビビりました。ら、3 件とも菊地氏だったわけです。
その 3 件のうちの 1 つは、私の以下のポスト、
リディアン・クロマティック・コンセプトの「宙吊り」性は、近代文明・経済機構へのアンチだったりとかとも言ってるので、音楽理論にアンチ資本主義ってあるの!?!?? ていう点でやっぱり根本でカルトなのでは… と思ったり。ここまで来ると、音楽理論も哲学的思考の対象になるんですよね〜〜〜
に対する次のようなリプライだったのですが、
そこがカルトなのでは笑(菊地成孔 ラッセルは宇宙と惑星間の引力の話もしますけど笑)
菊地氏が誤解しているのは、私はリディクロの内容がカルトだったとは思っていません(というか内容詳しく知らないか忘れているため判断できない)。正しくは、リディクロの伝授方法が秘教的だからカルト的とも言えるよねという記憶を持っており、ただ、その記憶も、柿沼の論稿によれば誤りで、そうなると単なるカルトとは言い切れない、ということです。
リディクロの内容がカルト的かどうかは、正直、私には判断のしようがないのですが、逆に、カルトではない音楽理論とはどういう音楽理論なのでしょか? という疑問も、私には思い浮かびました。
神秘主義的な要素のある音楽理論はカルト的かもしれませんが、社会・経済的なメッセージ性を含むとそれはカルト、というのはやや過言かな、とも思います。
「音楽理論」の範囲をどこまで広げるかにもよりますが、あまりに物理現象にのみ根拠を求めすぎると、それは音響理論とどう見分けるのか。とは言え、「アンチ資本主義なコード進行」とか言い始めたら音楽批評との境界が曖昧になってきます。だったら単純に、コード進行とかモードとかそういう解釈だけすればそれで音楽理論は十分なのかというと、やはり、「なぜ気持ちよく聞こえるのか」をしっかり追求するなら、コードとかモードとかを分析するだけでは不十分・根拠薄弱で、そうなると音響理論とどう見分けるのか、といった、最初の問題に戻るわけです。
音楽理論はあくまで「音楽」の理論で、音楽は人間の活動の結果(だと私は思っています。最近読んだ本で、アンコウも歌う、みたいなことも書かれてありましたが(『魚の耳で海を聴く: 海洋お生物音響学の世界』(築地書店, 2025))、そうであっても歌 = 音楽かどうかを判断しているのは人間です)なので、他の人間活動から切り離した「純粋な音楽理論」というのはおそらく成立しません。
ここで音楽理論史を紐解きたいところですが、それほどの時間的余裕と力量が自分にはありませんので、代わりに、2023 年に出版されたボエティウス『音楽教程』の訳者・伊藤友計による解題を参考にします。
伊藤によれば、ダランベールに代表されるような試みもあったものの、「ラモー以降の理論家が今日に至るまで中世の影響から脱却し、近代科学の枠組みによってのみ音楽理論を説明し切ったということもない。西洋音楽は結局のところ数比との関係を完全撤廃するには至らず、西洋音楽理論は数比と科学との奇妙な混合状態にある」。
これを私なりに言い換えると、「なぜその数比だと美しいと言えるのか」に根拠を与えず、数比の計算にのみ没頭するような理論は、けっきょくは神秘主義を脱していない、音楽理論はカルト的な要素を拭いきれない、ということになります。
もしかしたら菊地氏も、「すべて音楽理論は合理性の皮を被った神秘主義である」といったご認識かもしれません、そうだった場合は、私も菊地氏の意見に賛成です。ただ、ここ数年は菊地氏の作品を追えておらず(著書、音楽作品ともに)、菊地氏の音楽理論観を私は把握できていません。
最後に・ひたすらアルゴリズムの「オススメ」の流れを眺めるだけになってしまった現代 X において、著名人からエゴサ・直接リプライをいただくというふるきよきミッド・テン年代までの Twitter を体験できるとは思ってもいませんでした。
そしてリプライにブログでお返事するという、外-アルゴリズム的なネット交流ができたのも、感慨深かったです。
生成 AI の使いすぎで統合力のだいぶ弱った脳みそで書いた駄文を最後までお読みいただき、ありがとうございました。