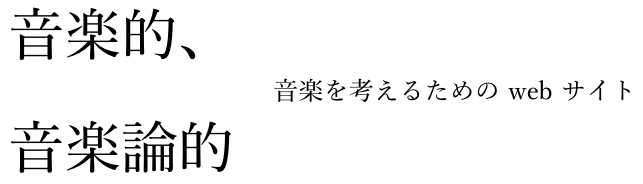最近、Dilla っぽい Beat の作り方を教える機会がありまして、ただ、その作り方というのも、自分が 2012 年頃だか 2013 年頃だかにちょろっと小耳に挟んだものを、ずっと「そういうもんなんだな」と思って実践している内容で、それが本当に理論的に大勢の支持を得ているのかどうか、というのが、自分のなかでは疑問でした。
Dilla のグルーヴをいかに再現するか?
その方法というのは、細かく区切った 3 連符 1 拍分ズレを作る、というもので、たとえば、ふつうに何のズレもなく、1/8 とか 1/16 とかグリッド線にぴったり合ったドラム・パターンを先に作っておいて、そのキック、スネア、ハイハットにズレを与えるのですが、ではどれくらいズレを作るのかというと、たとえば、1/64 の 3 連符 1 拍分、みたいな。1/64 の 1 拍分だと、ズレているかどうか、不自然ではないけど、ズレとしては認識出る。それと、3 連符ではない 1/64 の 1 拍分のズレと組み合わせたり、1/32 の 3 連符のズレも入れたり、などして、1/32 〜 1/64 の 1 拍分、3 連符も巧妙に取り入れてズレを取り入れることで、J Dilla っぽいビートを作ることができる。
これは、ズレているようで、実は細かく分割された 3 連符 1 拍分にしっかりクオンタイズされているので、人力で演奏したような、しかし実は機械的であるような、不思議なビートです。
というのを説明すると、だいたい音楽に詳しい人からは、「それってシャッフルでしょ?」(これは実はのちに書くように半分正解だったのですが)とか「それってスウィングでしょ?」とか、「それって坂本龍一がスコラで言ってたやつでしょ?」とかって反応されるんですけど、自分の中では「いや、そうではなく、ヒップホップ特有のクセのあるビートのことなんだよな・・・」と心の中で反論しつつ、面倒くさがりの口下手なので、反論は心の中で終わるのが常なのでした。
が、最近教えた方(MPC のオンラインレッスンで教えました)にはすんなり受け入れていただいて、伝わる人には伝わる(特にヒップホップ好きには)んだな、これ、と安心したのですが、それでも念の為、同じような考え方をしている人がいるのか、あるいは Dilla Beat の理論というのが、私の解釈(要するに、細かくした 3 連符 1 拍分ズレを作る)で合っているのか、というのを、ウェブで調べてみました。
ら、どうやら、2020 年頃から、日本のドラマー界隈では、5 連符あるいは 7 連符(あるいは9連符)のシャッフルを基本としたもの、といようなう考え方で定着しているようです。
2020 年 12 月、ドラムマガジンで紹介される
いま、YouTube で「Drunk Beat」「叩き方」とかって検索したら、だいたい 2020 年以降で、5 連符、7 連符から解釈した、ドラマー向けチュートリアル動画が公開されています。
で、2020 年 12 月に、ドラムマガジンで、Dilla Beat の叩き方が、譜面付きで紹介されています。
ドラムマガジンという権威ある雑誌でこのように譜面付きで紹介されているのであれば、もう、定説化していると言っても過言ではないでしょう。
DTM で Dilla Beat
では 2020 年以前はどうだったかというと、2019 年 12 月には、同じように 5 連符・7 連符の観点から DTM で Dilla Beat の作り方を紹介したサッキー氏による動画(およびブログ)が公開されていました。
5連符・7連符での DIlla Beat の再現: 日本での初出は、いつか?
さらにさかのぼると、2019 年 7 月に、ヒマラヤ氏による「ヨレたビートを叩くための練習方法」が、そしてこの記事は Yasei Collective 氏「4拍5連の基本と応用」を参考に書かれていて、「4拍5連の基本と応用」は 2019 年 3 月だったのですが、これ以前に、日本語で、Dilla Beat の作り方を 5連符・7連符の観点から説明しているウェブ上の情報は、私の知る限り見当たりませんでした。
なので、2019 年頃、おそらく、Yasei Collective さん周辺から(少なくともネット上では)情報が広がったのかも知れませんね。
もっと前の情報をご存知の方は、ぜひ、教えてください。
海外での、Dilla Beat の理論化
海外ではもっと前から知られていたようです。
まず、結論から言うと、私が見つけた中で一番ふるかったのは 2016 年の YouTube 動画ですね。
さきほど紹介したサッキー氏の DTM での解説記事・動画は、この辺を参考にされたのかも知れませんね。
見つけられた範囲で、5 連符を使っての Dilla Beat のドラム演奏の解説は、2017 年まで遡れました。
ちなみに 2012 年の同じテーマのドラム演奏解説動画には、5 連符といった言葉は出てきません。
なお 2018 年にはもうちょっと体系的な内容のブログ記事が公開されています。
この記事の素晴らしいところは、7連符や5連符を、では MPC の Swing 機能を使って再現しようとすればどうすればいいか? も解説されている点です。
この時点で Dilla の魔法は完全に明らかになっていた・・・ のかもしれません。
ということで、Dilla のフィールをいかに再現するか、その数値化の歴史を、ウェブで検索してみました。結果、私の見つけられる範囲では、2016 年が最も古い情報でした。
私が Dilla のフィールというか、いまのネオ・ソウルっぽいビートの魅力を知ったのは、2014 年の Mad Satta のアルバムで、
それから同じ時期にクリス・デイヴ、D’Angelo を知りました。記憶が正しければ、その頃は Robert Glasper が話題になって(『Black Radio』(2012))、日本でもズレたドラムの人気が一気に広がり、菊地成孔なんかがやかましかった記憶があります。
その頃、「ではどれくらいズレを作るとクリス・デイヴっぽくなるのか?」が熱く議論されており、そのなかで私が聞いたのが、細かく分割した 3 連符 1 拍分のズレでした。
その情報をずっとアップデートせずに、2025 年になってしまったのですが、日本では 2019 年頃、海外では 2016 年には、どうやらあの Dilla Beat を再現するのは 5 連符、7 連符、9 連符のシャッフルで再現できる、ということになっていたみたいです。
もっと古い情報を知ってるよ! という人は、ぜひ教えてください。
追記
YouTube チャンネルに、Dilla Beat の紹介動画をアップロードしました: https://youtube.com/shorts/Txq-UuiC4j4?si=n0J3mMMiT8xyylzq