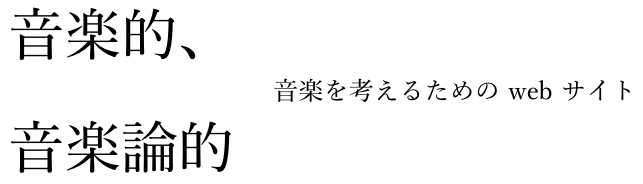音楽を聴くとき、私たちはどのようにその音を体験し、意味を見出すのでしょうか?
本ブログの「音楽の哲学史」シリーズ、前回の記事では、ダーウィン(Charles Darwin)やスペンサー(Herbert Spencer)、ガーニー(Edmund Gurney)の音楽と生命科学に関する思想を探求しました。
今回から 20 世紀の音楽思想。その第 1 回として音楽の現象学を取り上げます。音楽の現象学は、音楽体験の主観的な側面に焦点を当てた哲学的アプローチです。このアプローチを通じて、音楽がどのように知覚され、どのような意味を持つかを探ります。
フッサールの現象学
エトムンド・フッサール(Edmund Husserl, 1859–1938)は、現象学を哲学的方法として開発し、第一人称の経験を通じて客観性を基礎付けようとしました。フッサールは音楽についての観察をいくつか残しており、その中でも特に有名なのが、メロディの知覚体験を通じた時間意識の分析です。他の哲学者たちは、現象学的方法を採用して音楽の体系的な研究を行いました。
ロマン・インガルデン
ポーランドの哲学者ロマン・インガルデン(Roman Ingarden, 1893–1970)は、音楽の存在論に関する最初の体系的な調査の一つを行いました。インガルデンは現象学的方法を採用し、記述的アプローチを取ります。彼の言葉によれば、
「しかし、どれほど発展していようとも、具体的な事実に基づく理論は、初めの段階で方向を与えた体系的でない確信に依存しなければなりません」
この基盤に基づき、インガルデンは音楽作品を数学的な存在と同一視することを否定します。音楽作品は作曲されたときに初めて存在し、楽譜と同一ではありません。楽譜は音楽作品を記録する手段に過ぎず、演奏されることで具体化されますが、特定の主観的な体験と同一ではないと主張しました。音楽作品は意図的対象であり、経験する主体を必要としますが、特定の主観的経験と同一ではありません。また、音楽作品の時間性についても、演奏は時間の中で展開されますが、作品自体は時間的対象ではなく、「準時間的」(quasi-temporal)なものとされています。音楽作品の変化についても、楽譜によって正当な解釈が決定されるため、異なる時代の演奏の違いは作品自体の変化ではなく、価値観の違いに過ぎません。
アルフレッド・シュッツ
アルフレッド・シュッツ(Alfred Schutz, 1899–1959)の『音楽の現象学への断章』は、音楽が意味を持つが概念的または表象的な内容を欠くことを観察しました。シュッツは、音楽が時間の中で展開するため、音楽作品は多面的にしか把握できないと主張しました。音楽制作における作曲家、演奏者、聴衆の相互調整関係も探求しました。彼の論文『Making Music Together』(1951年)では、音楽制作に関わる様々なアクター(作曲家、演奏者、聴衆)間の「相互調整関係」を考察し、この関係が音楽作品の多面的な構成によって可能になると述べています。
現代における音楽の現象学
音楽現象学は現代でも広く採用されており、最近の研究にはクロフトンの音楽体験の現象学的分析が含まれます。音楽療法の分野でも、音楽がどのようにして感情を喚起し、心理的な治癒を促進するかを現象学的に分析しています。
結論
音楽の現象学は、音楽体験の主観的な側面に焦点を当て、音楽がどのように知覚され、どのような意味を持つかを探求する哲学的アプローチです。エトムンド・フッサールの現象学に基づき、ロマン・インガルデンやアルフレッド・シュッツの研究を通じて、音楽の存在論や時間意識、相互調整関係を分析します。音楽の現象学は、現代の音楽研究や音楽療法においても重要な位置を占めており、音楽体験の理解を深めるための貴重な視点を提供しています。